 ミミレイドン
ミミレイドンボス、おはようございます!
今朝のテーマは何でしょうか?



今朝も引き続きグループ通算制度と基礎について整理して行きたいと思います。



グループ通算制度の欠損金の取り扱いが複雑で正直よく分かりません。欠損金にフォーカスして整理してもらえませんか?というメッセージがありました。私も実は良くわかっていなくて。



それでは今朝はグループ通算制度の欠損金の取り扱いについて整理して行きたいと思います。
1.はじめに:グループ通算制度における繰越欠損金の控除限度額の取扱い
基本的な考え方
グループ通算制度は「個別申告方式」なので、繰越欠損金はグループ全体ではなく、各法人ごとに管理します。ただし、控除限度額(損金算入限度額)はグループ全体で計算します。
控除限度額の計算方法
グループ内の各法人の繰越欠損金控除前の所得金額の50%相当額の合計が上限となります。この「50%」というキャップは、法人ごとではなくグループ全体で設定されます。
特例(中小法人・更生法人・新設法人)
中小法人や更生法人、新設法人は、繰越欠損金を所得金額の100%まで控除可能となります。ただし、注意点として、中小法人等及び新設法人の判定については、通算グループ内のいずれかの法人が一社でも中小法人等または新設法人に該当しない場合には、その通算グループ内のすべての法人が中小法人等または新設法人に該当しないこととされますのでご注意ください。
2.特定欠損金と非特定欠損金の違い
グループ通算制度における欠損金は、「他の通算法人の所得と相殺できるか」という観点から、「特定欠損金」と「非特定欠損金」の2つに厳格に区分されています。
1. 特定欠損金(自分だけの赤字)
特定欠損金とは、一言で言えば「その法人自身の所得の範囲内でしか控除できない欠損金」です。他の通算法人が黒字であっても、その黒字と相殺(配分)することはできません。
主な該当項目
- グループ通算制度の開始前、またはグループ加入前に生じた「持ち込み欠損金」(時価評価除外法人(次項で解説)に該当する場合のみ持ち込み可能)。
- 通算グループ内で生じた欠損金のうち、共同事業性の欠如など特定の制限により損益通算の対象外とされたもの。
- 連結納税制度から移行した場合の「特定連結欠損金個別帰属額」。
最大の特徴(親法人の扱い)
従来の連結納税制度では、親法人の開始前欠損金はグループ全体で共有できる「非特定」扱いでしたが、グループ通算制度では親法人の一定の開始前欠損金も「特定欠損金」となり、親法人自身の所得からしか控除できなくなりました。
2. 非特定欠損金(みんなで共有できる赤字)
非特定欠損金とは、「通算グループ全体の所得から控除(共有)できる欠損金」です。
主な該当項目
- グループ通算制度を適用した後に、グループ内での損益通算を行ってもなお残った欠損金。
- 連結納税制度から移行した場合の「非特定連結欠損金個別帰属額」。
特徴
グループ全体の所得を上限として、グループ内のどの法人の所得からも控除できるため、節税メリットをグループ全体で享受しやすい性質を持ちます。
3. 計算順序と控除限度額のルール
欠損金の控除計算を行う際は、以下の優先順位に従います。
年度順
10年内の事業年度のうち、古いものから順に計算します。
区分順
同じ年度の欠損金であれば、「特定欠損金」から先に控除し、その後に「非特定欠損金」を控除します。
控除限度額
- 原則として、各法人の所得(損益通算後)の50%が控除の限度となります。
- ただし、グループ全員が中小法人等に該当する場合は、所得の100%(全額)まで控除可能です。



後ほど解説しますが、欠損金通算の計算は、通算グループ全体の損金算入限度額合計を基礎に、特定欠損金・非特定欠損金を各法人へ配賦して損金算入額を確定します。
3.欠損金の持ち込みが可能な時価評価除外法人とは?
グループ通算制度における「時価評価除外法人」とは、制度の開始時やグループへの加入時に、保有する資産の時価評価損益の計上(時価評価課税)を要しない法人のことです。
通常、グループ通算制度を開始または開始後に加入する場合、納税単位が変わるため、原則としてその直前に保有資産を時価評価して含み損益を清算する必要がありますが、一定の要件を満たす法人は「除外」されます。
実務上、この判定が極めて重要なのは、時価評価除外法人に該当しない場合、それまでに抱えていた繰越欠損金(赤字)が全額切り捨てられてしまうためです。
以下に、時価評価除外法人となるための具体的な要件を整理します。
1. 制度開始時(入口)の要件
通算制度を開始する際、以下の法人は時価評価を行う必要がありません。
- 通算親法人
いずれかの子法人との間に完全支配関係の継続が見込まれる場合。 - 通算子法人
親法人との間に完全支配関係の継続が見込まれる場合。
※従来の連結納税制度では親法人は無条件で対象外でしたが、通算制度では「継続見込み」という要件が必要になっています。
2. 加入時(途中参加)の要件
制度開始後、新たにグループに加わる法人が以下のいずれかに該当すれば、時価評価は不要です。
- グループ内の新設法人。
- 適格株式交換等により加入した子法人。
- 適格組織再編と同等の要件を満たす法人
◦ 加入前から支配関係がある場合:従業員や主要事業の継続見込みなど。
◦ 加入前から支配関係がない場合:上記に加え、親法人事業との関連性や、事業規模が5倍以内であること(または役員の継続)などの「共同事業要件」を満たすこと。
3. 時価評価除外法人となるメリット
- 資産の含み益への課税回避
時価評価を行わないため、帳簿価額が維持され、含み益に対する課税が発生しません。 - 欠損金の持ち込みが可能
時価評価除外法人が持つ繰越欠損金は、切り捨てられずにグループへ持ち込むことができます。ただし、この欠損金は原則として「特定欠損金」となり、その法人自身の所得の範囲内でしか控除できないという制限がつきます。



グループ通算制度を開始または制度へ加入する際、過年度に生じた欠損金額(繰越欠損金)は、原則として全額切り捨てとなりますが、「時価評価除外法人」に該当し、かつ特定の要件を満たす場合は、その法人自身の所得の範囲内でのみ控除できる「特定欠損金」としてグループ内へ持ち込むことができると覚えておきましょう。
ただ、時価評価除外法人であっても、「共同事業性がない」と判断される場合で、一定の条件に該当すると欠損金が切り捨てられますので、ご注意ください。
4.当期欠損金の配賦計算例
グループ通算制度における損益通算(欠損金の配賦)の簡単な計算例を解説します。こちらで配賦計算のイメージを付けてください。
損益通算の計算は、グループ全体の所得と欠損のどちらが多いかによって、配賦の基準が変わります。
1. 損益通算の計算ルール(比例配分(プロラタ)計算)
損益通算は以下の2ステップで行われます。
- 所得法人側(損金算入)
欠損法人の欠損合計額(所得合計額が上限)を、各所得法人の所得の比で配分し、各社の損金の額に算入する。 - 欠損法人側(益金算入)
上記1で所得法人側が損金算入した合計額を、各欠損法人の欠損の比で配分し、各社の益金の額に算入する。
2. 具体的な計算例(国税庁Q&A問49の数値を参照)
パターンA:所得の合計が欠損の合計より多い場合
(前提:所得合計 600 > 欠損合計 300)
| 項目 | P社(所得) | S1社(所得) | S2社(欠損) | S3社(欠損) | グループ合計 |
| ① 通算前所得(欠損) | 500 | 100 | △50 | △250 | 所得 600 / 欠損 300 |
| ② 損益通算(配賦額) | △250 (注1) | △50 (注1) | 50 (注2) | 250 (注2) | – |
| ③ 損益通算後の所得 | 250 | 50 | 0 | 0 | 300 |
(注1)所得法人の計算:欠損合計 300 を、所得比(P社 500:S1社 100 = 5:1)で按分して損金算入。
(注2)欠損法人の計算:欠損合計 300 がすべて相殺されるため、自社の欠損額と同額を益金算入(結果として所得0)。
パターンB:欠損の合計が所得の合計より多い場合
(前提:所得合計 300 < 欠損合計 600)
| 項目 | P社(所得) | S1社(所得) | S2社(欠損) | S3社(欠損) | グループ合計 |
| ① 通算前所得(欠損) | 250 | 50 | △500 | △100 | 所得 300 / 欠損 600 |
| ② 損益通算(配賦額) | △250 (注3) | △50 (注3) | 250 (注4) | 50 (注4) | – |
| ③ 損益通算後の所得 | 0 | 0 | △250 (注5) | △50 (注5) | △300 |
(注3)所得法人の計算:所得合計 300 が上限となるため、自社の所得額と同額を損金算入(結果として所得0)。
(注4)欠損法人の計算:所得法人側で損金算入された合計 300 を、欠損比(S2社 500:S3社 100 = 5:1)で按分して益金算入。
(注5)翌期への繰越し:損益通算で相殺しきれなかった欠損金(S2社 △250、S3社 △50)は、翌事業年度へ繰り越されます。
3. 実務上のポイント
- 遮断措置の適用
当初申告後にいずれか一社の所得金額に誤りが見つかった場合でも、原則として他社の損益通算額(配賦額)は当初申告の数値に固定されます。これにより、一社の修正でグループ全社が再計算を強いられる負担を回避しています。 - 全体再計算の例外
原則は遮断措置により他法人への影響は遮断されますが、法令上、一定の場合には遮断措置が適用されず通算グループ全体で再計算となることがあります。
5.通算法人の過年度欠損金額の損金算入額の計算方法
それでは、もう少し実務的で具体的な計算方法を見ていきましょう。
グループ通算制度における過年度の欠損金額の損金算入額の計算は、グループ全体を1つの法人とみなして計算した控除可能額を、各社の所得や税務上の制限に応じて配分する複雑なステップを踏みます。
1. 計算の基本原則
欠損金の控除計算を行う際は、以下の優先順位に従って、10年内事業年度(古い年度)から順次計算を行います。
1. 特定欠損金(その法人の所得の範囲内でのみ控除可能なもの)の計算。
2. 非特定欠損金(グループ全体の所得から共有して控除可能なもの)の配分および控除額の計算。
なお、損金算入限度額は、原則として損益通算後の所得金額の50%(中小法人等の場合は100%)となります。
2. 具体的な計算ステップ
各法人の計算プロセスを3つのステップで説明します。
ステップ①:特定欠損金の損金算入額の計算
まず、自社のみの所得で相殺すべき「特定欠損金」を先に控除します。
- 計算式
各通算法人の「特定欠損金額(控除前所得が上限)」を、グループ全体の「損金算入限度額の合計」の比率で配分した特定損金算入限度額を計算し、その範囲内で損金算入します。 - ポイント
特定欠損金は他の法人の所得と相殺することはできません。
ステップ②:各法人への非特定欠損金の配賦
次に、グループ全体の「非特定欠損金」を、控除枠が残っている法人へ割り振ります(比例配分(プロラタ)計算)。
- 計算式
グループ全体の「非特定欠損金の合計額」を、各法人の「特定欠損金控除後の損金算入限度額(残りの枠)」の比で按分します。 - 結果
これにより、自社に欠損金がない法人であっても、グループ内に非特定欠損金があれば、自社の所得枠に応じて欠損金が「配賦」されてきます。
ステップ③:非特定欠損金の損金算入額の計算
最後に、配賦された欠損金が実際にいくら損金算入できるかを確定させます。
- 計算式
ステップ②で配賦された額に、グループ全体の非特定損金算入割合(グループ全体の残り所得枠 ÷ グループ全体の非特定欠損金合計)を乗じて算出します。 - 最終的な損金算入額
「特定欠損金の損金算入額」+「非特定欠損金の損金算入額」の合計となります。
3. 数値による計算例(国税庁Q&A問54参照)
所得のあるP社、S1社、S2社の3社(いずれも大法人)の例です。
| 項目 | P社 | S1社 | S2社 | グループ合計 |
| ① 欠損控除前所得 | 220 | 80 | 180 | 480 |
| ② 損金算入限度額(①×50%) | 110 | 40 | 90 | 240 |
| ③ 繰越欠損金(内、特定分) | 150 (0) | 120 (50) | 300 (0) | 570 (50) |
| ④ 特定欠損金控除額 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| ⑤ 残りの限度額 (②-④) | 110 | 0 | 90 | 200 |
| ⑥ 非特定欠損金配賦額 | 286 | 0 | 234 | 520 |
| ⑦ 非特定欠損金控除額 | 104 | 0 | 86 | 190 |
| ⑧ 合計控除額 (④+⑦) | 104 | 50 | 86 | 240 |
特定欠損金額の損金算入額
特定欠損金額の損金算入額は、その10年内事業年度の特定欠損金額のうち、特定欠損金額の損金算入限度額(以下「特定損金算入限度額」といいます。)に達するまでの金額となります。
損金算入限度額=イ×ロ÷ハ
イ:その通算法人のその10年内事業年度の特定欠損金額(欠損控除前所得金額を限度)
ロ:各通算法人の適用事業年度に係る損金算入限度額の合計額
ハ:各通算法人のその10年内事業年度に係る特定欠損金額(欠損控除前所得金額を限度)の合計額
なお、上記算式におけるロの金額がハの金額に占める割合が1を超える場合には、その割合を1として計算し、ハの金額が零の場合は、その割合は零として計算します。
上記計算例を当てはめるとイ50×ロ240÷ハ50となりますが、ロの金額がハの金額に占める割合が1を超える場合には、その割合を1として計算するため、50×1となり、特定欠損金控除額は50となります。
非特定欠損金額の損金算入額
非特定欠損金額の損金算入額は、その10年内事業年度の非特定欠損金額のうち、非特定欠損金額の損金算入限度額(以下「非特定損金算入限度額」といいます。)に達するまでの金額となります。
非特定損金算入限度額の計算を行う場合には、まず、その10年内事業年度に生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額の通算グループ全体の合計額を各通算法人に配賦して、各通算法人の非特定欠損金額を計算します。この非特定欠損金額とは、その10年内事業年度に通算法人で生じた特定欠損金額以外の欠損金額に、①次のAの算式により計算した金額(以下「非特定欠損金配賦額」といいます。)がその特定欠損金額以外の欠損金額を超える場合にはその超える部分の金額(以下「被配賦欠損金額」といいます。)を加算し、②非特定欠損金配賦額がその特定欠損金額以外の欠損金額に満たない場合にはその満たない部分の金額(以下「配賦欠損金額」といいます。)を控除した金額をいいます。
すなわち、通算グループ全体の特定欠損金額以外の欠損金額の合計額を、各通算法人のそれぞれの損金算入限度額の比で配賦した金額が、この非特定欠損金額となります。
A:非特定欠損金配賦額=イ×ロ÷ハ
イ:各通算法人のその10年内事業年度に係る特定欠損金額以外の欠損金額の合計額
ロ:その通算法人の適用事業年度の損金算入限度額
ハ:各通算法人の適用事業年度に係る損金算入限度額の合計額
上記計算例を当てはめると、⑥非特定欠損金配賦額はそれぞれ次のように計算されます。
P社:520×110÷200=286
S1社:520×0÷200=0
S2社:520×90÷200=234
B:非特定損金算入限度額=イ×ロ÷ハ
イ:その通算法人のその10年内事業年度の非特定欠損金額(上記⑥の金額)
ロ:各通算法人の適用事業年度に係る損金算入限度額の合計額
ハ:各通算法人のその10年内事業年度に係る特定欠損金額以外の欠損金額の合計額
上記計算例を当てはめると、⑦非特定欠損金控除額はそれぞれ次のように計算されます。
P社:286×190÷520=104
S1社:0×190÷520=0
S2社:234×190÷520=86
4. 実務上の留意事項
• 連結納税からの引継ぎ: 連結納税制度から移行した場合、従来の「特定連結欠損金」は「特定欠損金」として、「非特定連結欠損金」は「非特定欠損金」として引き継がれます。
• 親法人の欠損金: グループ通算制度では、通算親法人の開始前欠損金も「特定欠損金」として扱われるため、自身の所得からしか控除できない点に注意が必要です。
• 通算税効果額: 欠損金の通算によって税負担が軽減された場合、そのメリット分を法人間で精算(授受)することが一般的ですが、このやり取りは税務上の益金・損金には算入されません。
参照:通算法人の過年度の欠損金額の当初申告における損金算入額の計算方法|国税庁
6.修正申告等があった場合
グループ通算制度において、税務調査や誤りの発見により修正申告又は更正(以下「修更正」)が生じた場合、過年度の欠損金の損金算入額の計算は、実務負担を軽減するための「遮断措置(しゃだんそち)」という独自のルールに基づき行われます。
1. 計算の基本原則:遮断措置(影響の遮断)
グループ通算制度では、グループ内の一社の所得や欠損金に変動が生じても、「他の通算法人の損金算入額」は当初申告の金額で固定(遮断)されます。これにより、一社の修正でグループ全社が雪崩式に再計算を強いられることを防いでいます。
- 影響を受けない法人
当初申告の「損金算入限度額」や「配分された欠損金額」をそのまま使い続けるため、再計算の必要はありません。 - 修更正を行う法人
自社のみで、当初申告の数値を一定のルールで固定・調整した上で、再計算を行います。
2. 修更正を行った法人の損金算入額の計算方法
国税庁の指針によれば、修更正を行う法人の過年度欠損金の損金算入額は、以下の「(1)被配賦欠損金控除額」と「(2)自社の残り枠での控除額」の合計額となります。
(1) 被配賦欠損金控除額(もらった赤字の固定)
当初申告において、「他の法人から分けてもらった(配賦された)欠損金」のうち、自社の所得で控除した金額です。この金額は、修更正後もそのまま損金算入額として認められます。
(2) 自社の欠損金の損金算入額(残り枠での調整)
自社がもともと持っていた欠損金のうち、「当初申告で他社へ分けてあげた分」を除いた残りについて、以下の調整後の限度額に達するまで損金算入します。
- 使用する欠損金額
自社の過年度欠損金 - 当初申告で他社に配賦(提供)した額。 - 調整後の損金算入限度額
修更正後の限度額(所得の50%等)に、当初申告で他社から譲り受けた「枠(限度額)」があれば加算し、他社へ譲り渡した「枠」があれば控除し、さらに上記(1)の金額を差し引いた残額です。
3. 遮断措置が適用されない場合(全体再計算)
以下の要件に該当する場合は、例外的に遮断措置を適用せず、グループ全員で最初から計算をやり直す「全体再計算」が行われます。
- グループ全体が欠損超過
通算グループ内の全ての法人の損益通算後の所得が0以下であるなど、一定の要件を満たす場合。 - 租税回避と認められる場合
欠損金の繰越期間制限を逃れる目的や、離脱法人に欠損金を不当に帰属させるためにあえて誤った当初申告を行ったと認められる場合。
参照:国税庁 修正申告等があった場合の通算法人の過年度の欠損金額の損金算入額の計算方法
7.通算子法人同士の適格合併が行われた場合の欠損金額
通算グループ内の通算子法人同士で適格合併が行われた場合の欠損金額の取扱いについて、具体的に解説します。
主なポイントは、「合併直前事業年度に生じた欠損金」と、それより前に生じていた「過年度の繰越欠損金」で扱いが異なる点にあります。
1. 合併直前事業年度に生じた欠損金の取扱い
被合併法人(消滅する子法人)が、合併の日の前日に終了する事業年度(最後事業年度)において赤字(欠損金)を出した場合の取扱いは以下の通りです。
- 損益通算の不適用
通算子法人が合併により解散する場合、合併の日をもって通算承認の効力が失われます。このため、合併直前の事業年度は親法人の事業年度終了の日に終了しないことから、グループ内での損益通算(当期の黒字・赤字の相殺)の規定は適用されません。 - 合併法人での損金算入
損益通算は適用されませんが、その欠損金額に相当する金額は、法人税法第64条の8の規定により、合併法人(存続する子法人)の合併日の属する事業年度において損金の額に算入されます。
2. 過年度から繰り越された欠損金の取扱い
被合併法人が合併前から持っていた過年度の繰越欠損金は、適格合併によって合併法人に引き継がれますが、その種類(特定・非特定)が維持されます。
- 特定欠損金の引継ぎ
被合併法人が持っていた「特定欠損金額」に達するまでの金額は、合併法人においても「特定欠損金額」とみなされます。これは、合併法人の所得の範囲内でのみ控除可能です。 - 非特定欠損金の引継ぎ
特定欠損金額以外の欠損金額は、合併法人において「特定欠損金額以外の欠損金額(非特定欠損金)」として引き継がれます。こちらはグループ全体の所得から控除可能な共有の欠損金として扱われます。
数値を用いたイメージ例
(前提:子法人S2が子法人S1に吸収合併されるケース)
| 欠損金の種類 | 被合併法人(S2)の状況 | 合併法人(S1)への引継ぎ・処理 |
| ① 合併直前事業年度の赤字 | 1,000円の赤字発生 | S1の当期損金として1,000円算入 |
| ② 過年度の特定欠損金 | 500円保有 | S1の特定欠損金として500円承継 |
| ③ 過年度の非特定欠損金 | 300円保有 | S1の非特定欠損金として300円承継 |
このように、適格合併が行われると、被合併法人が精算しきれなかった赤字は、原則として合併法人がその性質を引き継いで活用できる仕組みになっています。
参照:国税庁 通算グループ内の通算子法人同士の適格合併が行われた場合の被合併法人の欠損金額の取扱い
8.まとめ
グループ通算制度では、欠損金は法人ごとに管理される一方、欠損金の損金算入額は「損金算入限度額(原則:所得の50%、一定法人は所得金額)」という枠を用いて、通算グループ全体の計算として配賦・確定していきます。欠損金は「特定欠損金」と「特定欠損金以外(非特定)」に区分され、同一年分では特定欠損金から優先して控除する点が実務上の重要ポイントです。
また、通算制度の開始・加入時には過年度欠損金が原則として切り捨てとなり得ますが、時価評価除外法人に該当するなど一定の要件を満たす場合には、特定欠損金として持ち込みが可能となります。さらに、当期の損益通算は所得・欠損の状況に応じて比例配分で行われ、修正申告等が生じた場合でも原則として遮断措置により他法人への影響が固定される仕組みです。制度の入口(開始・加入)と欠損金区分、そして限度額・配賦の考え方を押さえることが、誤りのない申告実務につながります。



昨日までのグループ通算制度に関する記事は、以下の通りとなりますので、よろしければご覧ください。
グループ通算制度の基礎①:制度の全体像と導入の背景
グループ通算制度の基礎②:通算所得・通算税額の計算と実務の流れ
グループ通算制度の基礎③:各種規定の取り扱い(通算前所得の計算)
グループ通算制度の基礎④:各種規定の取り扱い(グループ全体で計算・調整する規定)


編-300x169.jpg)




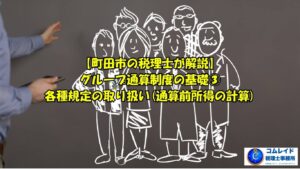


コメント