 ミミレイドン
ミミレイドンボス!いよいよ独立開業ですね!



そうだね。どんなお客様とお仕事ができるのか今から楽しみだね!
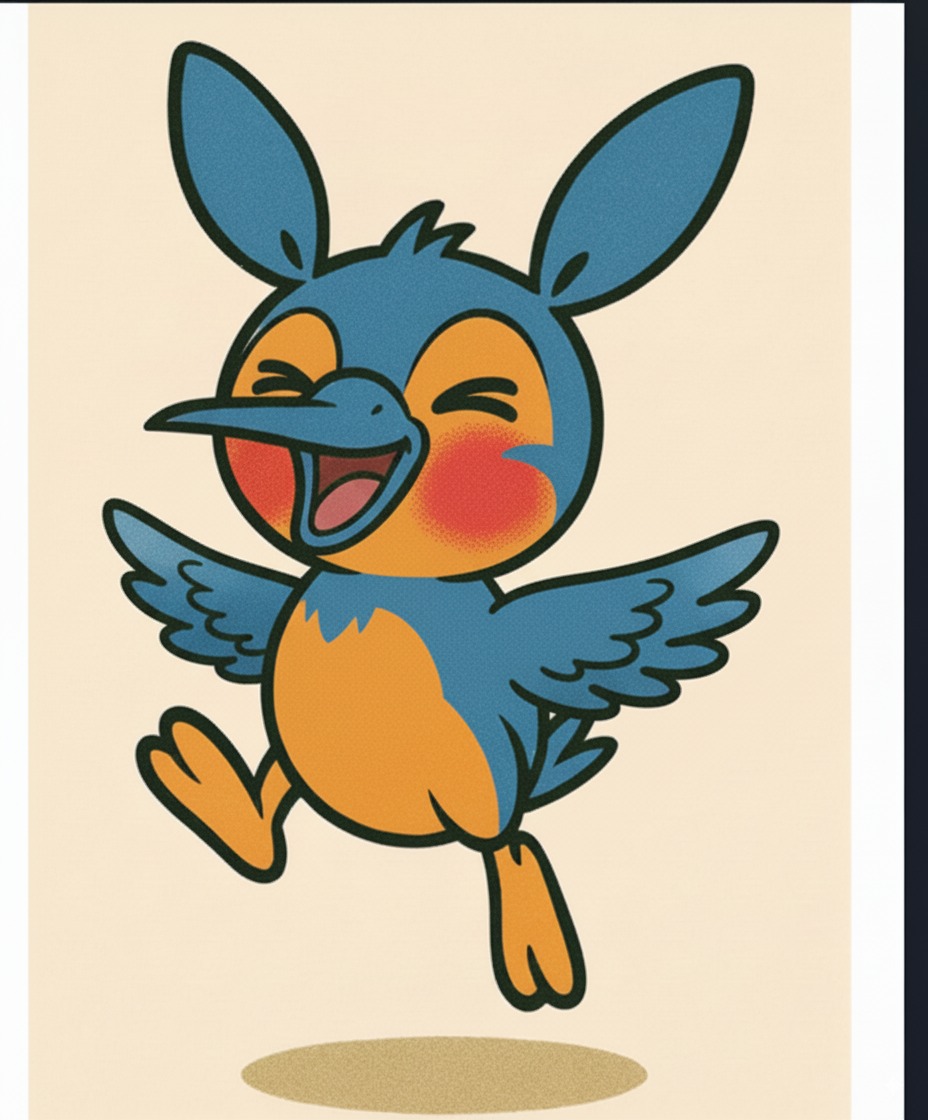
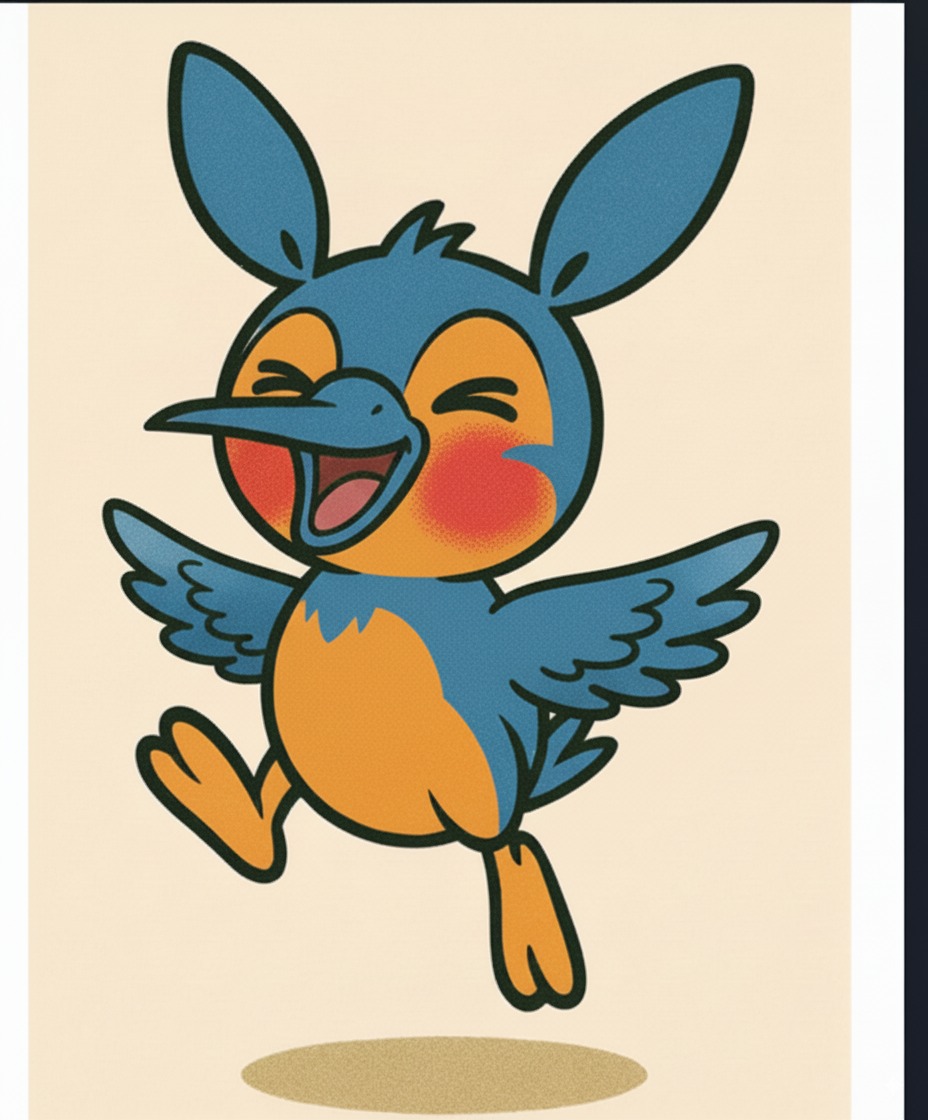
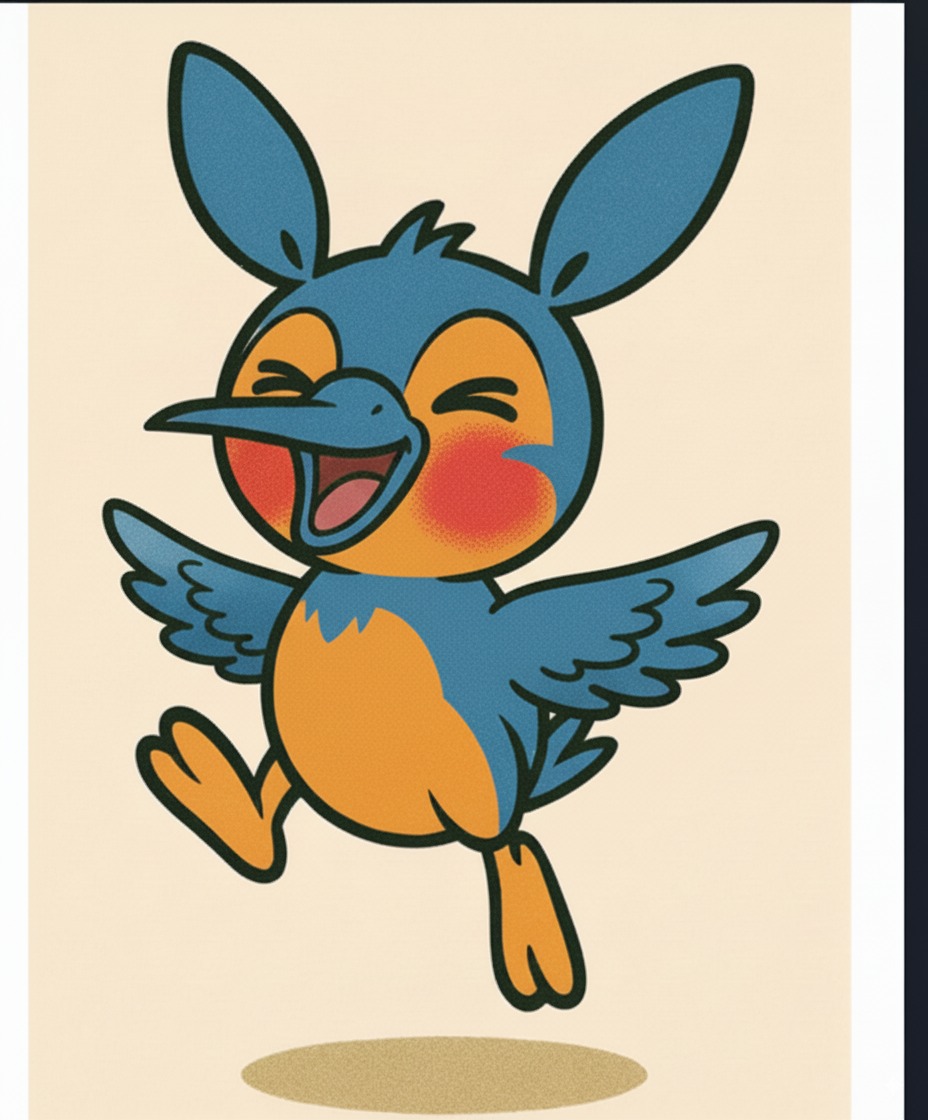
多くのお客様とお仕事できるようにたくさんPRしていかないとですね!



頼むよ!事務所の広報部長!



ところでボス。独立開業するときの手続きって何かあるんでしたっけ?何から始めたらいいのかわからなくていきなり不安になってきました。。。



それじゃあ、個人事業主が開業する際の必要手続きについて、説明していくね。実は手続き自体はとてもシンプルなんだけど、後々の税務や経理に直結する大事なステップでもあるんだ。税理士として見てきた“つまずきポイント”なんかも踏まえて解説するね。
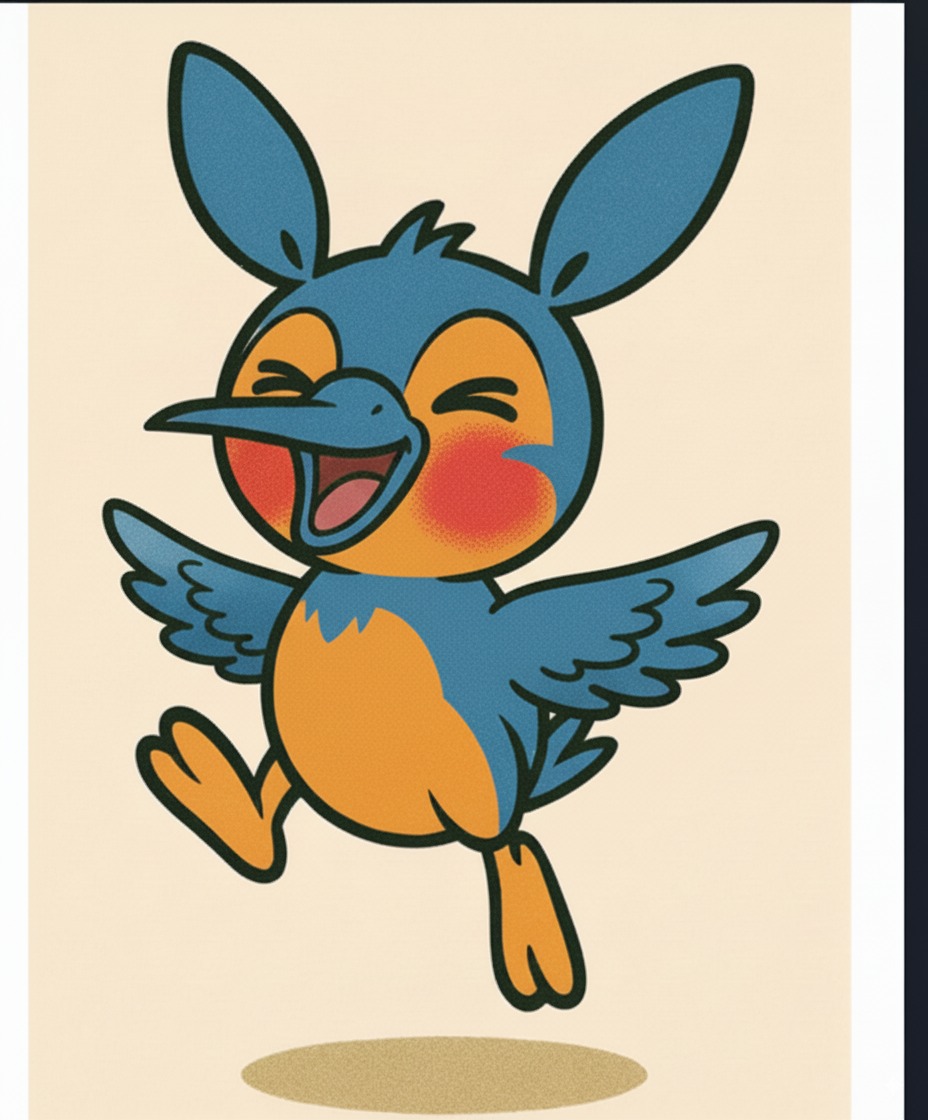
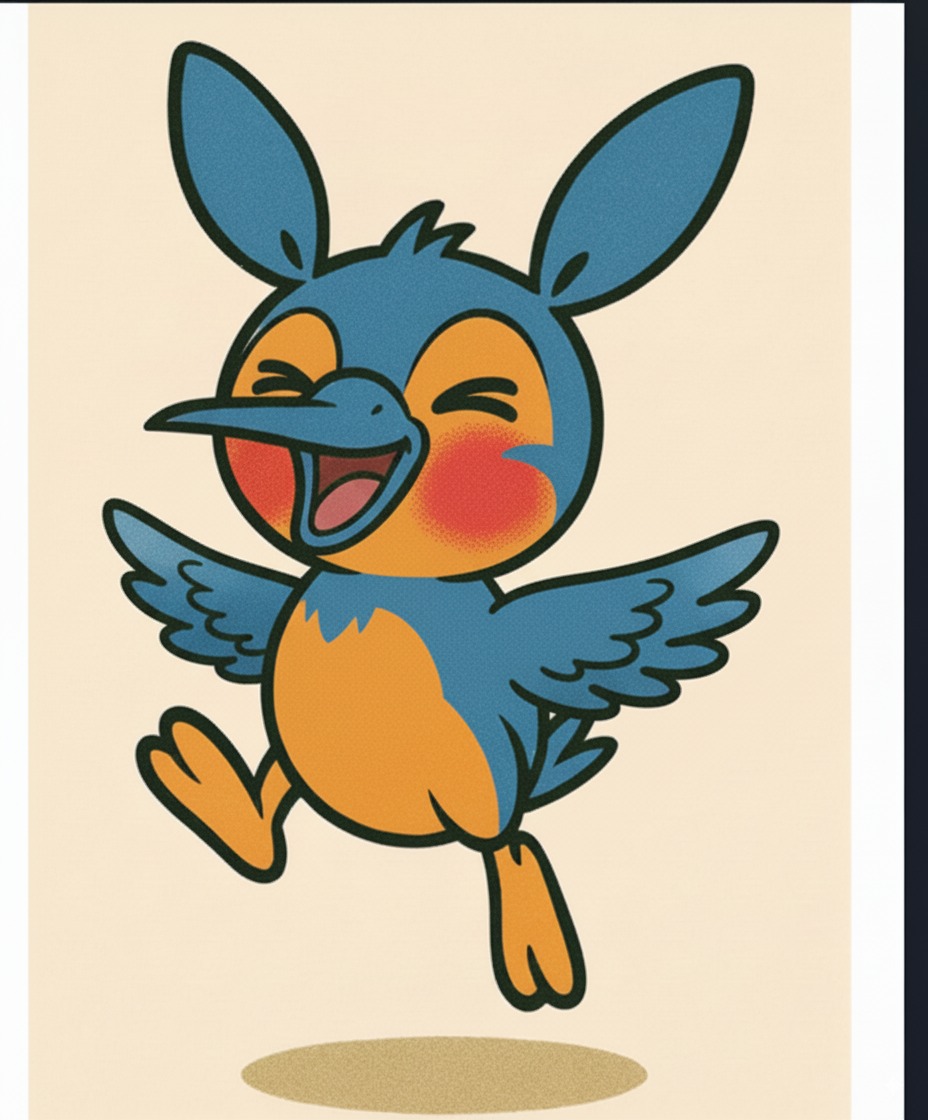
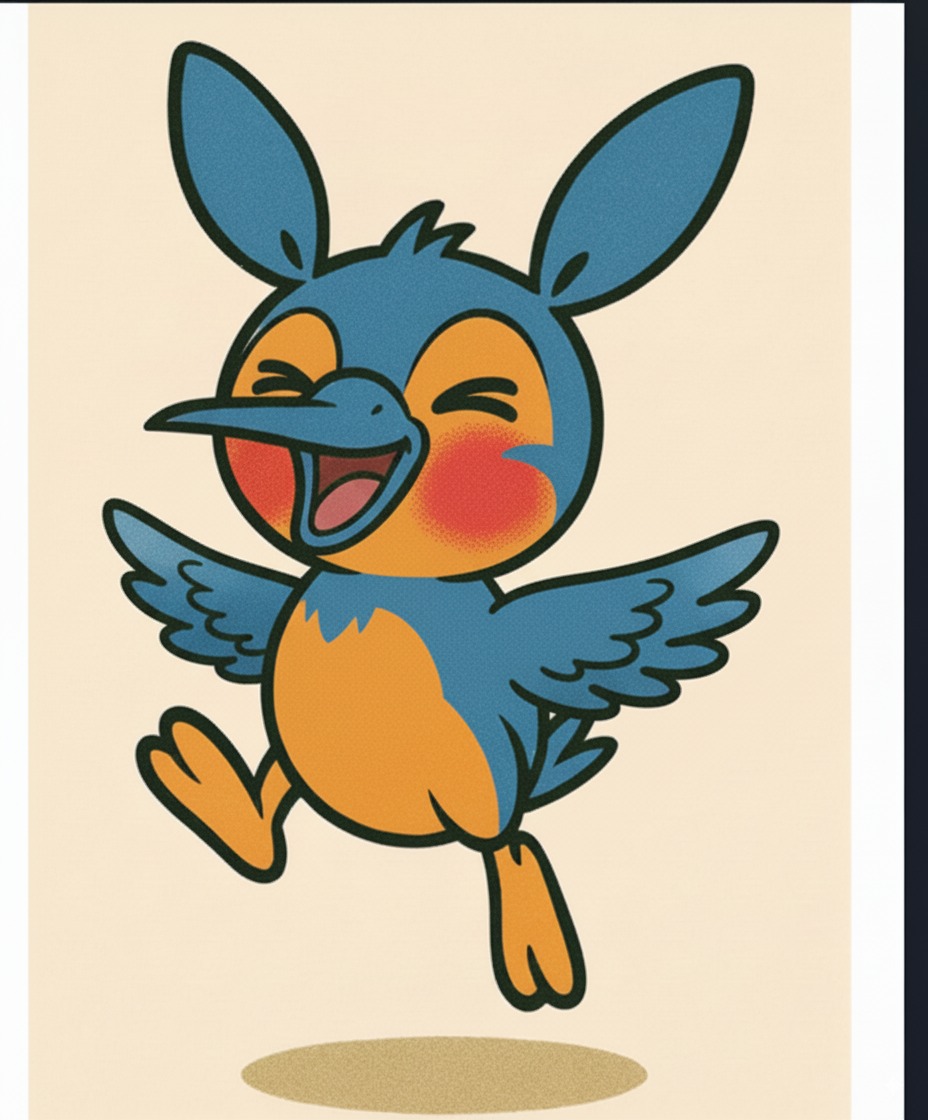
よろしくお願いします!この記事の最後にお得なキャンペーン情報も記載してます。
0.個人事業主・フリーランスの開業までの全体フロー



まずは、手続きの簡単な流れを把握した後、各論点を見ていきましょう。
0-1_準備段階(事業内容・屋号・事業所所在地の決定)
「よし、独立してやっていくぞ!」と決意した瞬間から、あなたはもう立派な起業家の第一歩を踏み出しています。
でも、いざ動き出そうとすると――
- 何から決めればいいの?
- 屋号ってどうやって考えるの?
- 住所は自宅でもいいの?
そんな疑問が次々と湧いてくるはず。
今回は、開業届を出す前に必ず決めておきたい3つのポイントを、わかりやすく解説します。
0-2_開業届・青色申告承認申請書等の提出
開業届出は、あなたの「開業宣言書」となります。
また、青色申告承認申請書は、青色申告をするための事前申請書です。
これを出しておくと、税務面で大きなメリットがあります。
0-3_社会保険関連の届出
事業とは直結しないため、国保・国民年金への切り替えを失念するケースがあります。
開業するための大切な手続きだと思って、しっかりと手続きをしましょう。
0-4_必要に応じた許認可申請
開業届を提出すれば安心!というわけではありません。業種によっては営業開始前に許可や届出が必須となるため、実施する業種に必要な許可等の有無について、事前確認を怠らないことが重要です。
0-5_銀行口座・クレジットカード・会計ソフトの準備
必ず必要な手続きではありませんが、開業前後で取り掛かりたい項目をいくつか案内しております。例えば、銀行口座やクレジットカードは、事業用とプライベートを分けて管理することで、経理がシンプルになり確定申告もスムーズになります。



「許可=審査を経て認められるもの、届出=必要事項を提出すれば原則受理されるもの」ということだよ!
1.開業届の提出
(1)開業届出の作成
開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、
「私はこの日から事業を始めます」と税務署に知らせるための書類です。
記入内容は、氏名・住所・屋号・事業の概要など、
非常にシンプルですが、屋号や事業内容は今後の名刺や口座開設にも関わるので丁寧に検討することが重要です。
正式名称は「個人事業の開廃業等届出書」といい、事業を開始してから1カ月以内に管轄の税務署に提出します。届出書を見ると、記載欄が多く感じるかもしれませんが、実は非常にシンプルです。必要事項(氏名、住所、事業の概要など)をしっかりと記載していれば、受理されますので、まずは、必須事項を決めていきましょう。屋号や事業内容は今後の名刺や口座開設にも関わるので丁寧に検討することが重要です。
①事業内容を決める
「何をして、誰に、どうやって」提供するか
事業内容は、開業届にも記載する重要項目です。
ここで大事なのは、できるだけ具体的に書くこと。
たとえば――
- ❌「コンサルティング業」
- ⭕「中小企業向け経営改善コンサルティング」
具体的にすることで、後の営業活動や補助金申請、銀行口座開設でも信頼度がアップします。



例えば、「Web制作・SNS運用代行・広告コンサルティング」など、将来やる可能性のある業務も、関連性があれば一緒に書いておくと便利です。



この段階で事業計画や資金計画を立てることもとても重要ですよね。



そうだね。事業計画や資金計画の作成まで言及するとドンドン話がそれていくから、また別の記事にしましょうか。焦らず一個ずつコツコツと進めるのがポイントです。一気にやろうとすると、挫折するから自分のペースで一緒に頑張りましょう。
②屋号を決める
名刺・請求書・ホームページの“顔”になる名前
屋号は、いわばあなたの事業のブランド名。
必ずしも必要ではありませんが、信頼感や覚えやすさを考えると付けた方が有利です。
決め方のポイントは3つ:
- 覚えやすい(短く、発音しやすい)
- 意味が伝わる(業種や想いがイメージできる)
- 検索しやすい(同業他社と被らない)



商標登録やドメイン取得の可否も事前にチェックしておくと良いかもしれません。ローマ字表記や英語表記も考えておくと、SNSやメールアドレスで統一感が出てカッコ良いです。ちなみに、「屋号」の命名は必須ではありませんが、事業用の口座開設などのメリットがあります。



ボスも最後まで「新屋賢人税理士事務所」にするか迷ってましたね。



税理士にとって自分の名前を事務所名にするのは夢でありステータスだからね。でも、単なる委託先ではなく、お客様の”同志”としてやっていきたいという想いを前面に出したかったから、”コムレイド”税理士事務所にしたんだ。
③事務所所在地を決める
自宅か?レンタルオフィスか?
開業届には、事業所の住所を記載します。
自宅を使う人も多いですが、業種やプライバシーの観点から選択肢を検討しましょう。
主な選択肢と特徴
| 選択肢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自宅 | コストゼロ、すぐ始められる | 住所が公開され、来客対応に不向き |
| レンタルオフィス | 住所利用OK、打合せスペースあり | 月額費用がかかる |
| バーチャルオフィス | 住所だけ借りられる、安価 | 実作業スペースは別途必要 |



郵便物の受け取りや銀行口座開設で住所証明が必要になる場合あります。 また、将来移転する可能性があるなら、名刺やサイトの住所表記は柔軟に変更できる設計にしておく方が良いかもしれません。
(2)開業届出の入手方法
国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署で入手できます。e-Taxでの電子申請、郵送、直接持参のいずれかの方法で提出します。
(3)提出先と提出期限
事業所所在地を管轄する税務署に対して、開業から1か月以内に提出する必要があります。
(4)提出方法(窓口・郵送・e-Tax)
e-Taxでの電子申請、郵送、直接持参のいずれかの方法で提出します。e-Taxの準備ができていない方も多いと思いますので、郵送や直接持参で問題ありません。



立場上、言おうか悩んだのですが、実は提出期限(開業から1か月以内)を過ぎても罰則はありません。ただし、テナント賃借、銀行口座開設や融資の際に「開業届の写し」を求められるケースがあるため、提出しておくことがスムーズな事業展開に役立ちますので、必ず提出するようにしましょう。
2.青色申告承認申請書
(1)青色申告承認申請書とは
青色申告承認申請書は、青色申告をするための事前申請書です。
こちらを出しておくと、以下のような大きなメリットがあります。
- 最大65万円の特別控除(満額(65万円)控除の要件として、複式簿記+電子申告(e-Tax)などがあります。)
- 赤字を3年間繰り越せる
- 家族への給与を経費にできる
つまり、節税と経営の安定に直結する超重要書類なのです。
①提出期限
開業から2か月以内、またはその年の3月15日までとなります。
②提出先
開業届と同じ事業所所在地を管轄する税務署に提出する必要があります。私は開業届出と一緒に提出してしまってます。青色申告承認申請書の入手はこちらから。



期限を過ぎるとその年は白色申告になってしまうので注意が必要です。青色申告をするメリットは上記以外にもありますので、青色にするか白色にするか悩んでいる方は気軽にお問い合わせください。
(2)その他税務関連の届出書
①青色事業専従者給与に関する届出書
青色事業専従者給与に関する届出書を提出することにより、生計を一にする配偶者や親族に給与を支払った場合、その給与を必要経費として計上できます。事業主一人に所得が集中するのを防ぎ、家族に適正な給与を分配することで、全体の税負担を抑えることができます。詳細は、また別の記事で解説します。
開業初年度の提出期限は原則その年の 3月15日までとなりますが、1月16日以降に開業した場合や、新たに専従者を雇った場合は、開業日(または専従者がいることとなった日)から2か月以内が提出期限となります。青色事業専従者給与に関する届出書の入手はこちらから。



ご家族に給与を支給する予定がある場合には、開業届や青色申告承認申請書とセットで提出してしまいましょう。
②給与支払事務所等の開設届出書
給与支払事務所等の開設届出書とは、事業者が従業員に給与を支払う際に、源泉所得税の納付手続きを税務署に通知するためのものです。この届出書は、給与を支払う事務所を開設した場合等に、税務署へ届け出る必要がありますので、個人事業主の場合、従業員を雇用することとなった場合に提出が必要となります。「開設日」とは、従業員を初めて雇った日または初めて給与を支払った日のいずれかとなります。忘れないように、例えば、2025年5月15日に従業員を雇った場合には、1か月後の2025年6月15日までに提出するようにしましょう。給与支払事務所等の開設届出書の入手はこちらから。



提出を忘れても罰則はないため、提出を失念している人が多い印象ですが、提出をしないことにより、税務署に給与支払者として認識されず、税務署からのお知らせや納付書が届かないため、納付漏れとなるリスクが高まります。開業当初から従業員を雇用する場合には、開業届と一緒に提出してしまいましょう。
3.ちなみに・・・(国民健康保険と国民年金への加入)
会社を辞めて個人事業主となる場合は、国民健康保険(国保)と国民年金への加入手続きが必要です。いずれも退職の翌日から14日以内に市区町村役場の窓口で手続きを行います。 会社で加入していた健康保険を任意継続する選択肢もあり、最長2年間継続できます。 国民健康保険組合など、業種ごとに特化した保険組合に加入できる場合もあります。



社会保険の切り替えは、独立後の生活基盤を守る大切なステップです。
ここをしっかり押さえておけば、安心して事業に集中できます。ただ、意外と忘れがちな論点なので、しっかりと確認しておきましょう。
(1)国民健康保険(国保)に加入する
会社員時代は「社会保険(健康保険+厚生年金)」に加入していましたが、退職すると自動的に資格を失います。
そのため、退職の翌日から14日以内に、市区町村役場で国民健康保険の加入手続きを行う必要があります。
手続きに必要なもの
- 健康保険資格喪失証明書(前職の会社から受け取る)
- マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
- 印鑑(自治体によっては不要)



保険料は前年の所得を基準に計算されるため、独立初年度は「会社員時代の年収」で算出されることが多いです。思ったより高額になるケースもあるので注意が必要です。
(2)国民年金に加入する
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。
会社員時代は「厚生年金」に加入していましたが、退職後は自動的に国民年金に切り替える必要があります。
手続きの流れ
- 市区町村役場の年金窓口で申請
- 年金手帳または基礎年金番号通知書を持参
(3)健康保険の「任意継続」という選択肢
実は、会社員時代に加入していた健康保険を 最長2年間だけ継続できる制度 があります。
メリット
- 保険内容(給付や扶養制度)がそのまま使える
- 医療費の自己負担割合も変わらない
デメリット
- 保険料は全額自己負担(会社負担分がなくなるため、倍近くになることも)
(4)国民健康保険組合という選択肢
業種によっては、国民健康保険組合に加入できる場合もあります。
たとえば、医師・建設業・芸術関係など、特定の職種向けに設けられた組合です。
- 保険料が定額制のところもあり、所得が高い人に有利
- 業界特有の福利厚生サービスが受けられる場合も
ただし、誰でも入れるわけではないので、自分の業種で該当する組合があるか確認してみましょう。
4.業種によって必要な許認可
「開業届を出せばすぐに事業を始められる!」
そう思っている方も多いのですが、実は業種によっては 営業開始前に「許認可」 を取らなければなりません。
もし許認可を取らずに営業を始めてしまうと、営業停止や罰金といったペナルティを受ける可能性もあります。
この記事では、わかりやすいように、代表的な業種ごとの許認可を整理しました。なお、業種によって窓口が異なりますので、注意が必要です(保健所・警察署・都道府県庁・運輸局など)。



開業準備では「自分の業種に許認可が必要か」を必ずチェックしましょう。許認可手続きに時間を要することもありますので、スケジュールに余裕を持って申請することをおすすめいたします。
(1)飲食・食品関連(保健所が窓口)
- 飲食店営業許可:レストラン、カフェ、居酒屋など
- 菓子製造業許可:パン屋、ケーキ屋など
- 旅館業許可:ホテル、民宿、ゲストハウス



飲食店でアルコールを提供する場合は追加の免許は不要ですが、酒屋として販売する場合は税務署の「酒類販売免許」が必要です。
(2)美容・生活サービス関連(保健所が窓口)
- 理容所開設届:理容室・床屋
- 美容所開設届:美容室・サロン
- クリーニング所開設届:クリーニング店



これらは「届出」で済むケースが多く、比較的スムーズに手続き可能です。
(3)リサイクル・中古品関連(警察署が窓口)
- 古物商許可:リサイクルショップ、中古本屋、ブランド品販売
- 質屋営業許可:質屋



古物商許可は「盗品流通防止」の観点から厳格に管理されています。ネット販売でも中古品を扱う場合は必須です。
(4)娯楽・接客サービス関連(警察署が窓口)
- 風俗営業許可:キャバクラ、スナック、ホストクラブ
- 深夜酒類提供飲食店営業届出:深夜0時以降に営業するバー



「深夜営業」と「風俗営業」は別物です。バーを深夜まで営業するだけなら「届出」で済みます。
(5)不動産・建設関連(都道府県庁が窓口)
- 宅地建物取引業免許:不動産仲介業
- 建設業許可:建設業を営む場合
- 旅行業登録:旅行代理店
(6)運輸・自動車関連(運輸局・警察署が窓口)
- 貨物自動車運送事業許可:運送業
- 旅客自動車運送事業許可:タクシー・バス
- 自動車運転代行業認定:運転代行サービス
(7) その他の代表例
- 酒類販売免許(税務署):酒屋、ワインショップ
- たばこ小売販売許可(JT):たばこ販売店
- 有料職業紹介事業許可(ハローワーク):人材紹介業
5.開業後すぐにやっておくべきこと
(1)事業用銀行口座・クレジットカードの開設
個人事業主として開業したら、まずやっておきたいのが 「お金の流れを整理すること」。
その第一歩が、事業用の銀行口座とクレジットカードの開設です。
「個人の口座やカードでも使えるし、わざわざ分けなくてもいいのでは?」
そう思う方も多いのですが、実はここをきちんと分けるかどうかで、後々の経理や信用力に大きな差が出ます。
1. 事業用銀行口座を作るメリット
- お金の流れが一目でわかる
事業用口座を作る最大のメリットは、事業のお金とプライベートのお金を完全に分けられること。
売上の入金も経費の支払いもすべて事業用口座で完結させれば、通帳やネットバンキングを見ただけで「事業のお金の流れ」が一目瞭然です。
- 確定申告がラクになる
確定申告のときに「これは事業用?それとも個人用?」と仕分けに悩む必要がなくなります。
会計ソフトと連携すれば、自動で仕訳が進むので経理作業が一気に効率化することができます。
- 信用力アップ
屋号付き口座を持っていると、取引先や顧客からの信頼感も高まります。
「きちんと事業をしている人だ」と見てもらえるのは大きなポイントです。



個人の口座やカードでも使えるわけですし、わざわざ分けなくてもいいのではないでしょうか?



そう思う方も多いのですが、実はここをきちんと分けるかどうかで、後々の経理や信用力に大きな差が出るのです。
(2)会計ソフトの初期設定(勘定科目・消費税設定)
個人事業主として開業したら、まずやっておきたいのが 会計ソフトの初期設定。
「とりあえず入力を始めればいいんでしょ?」と思いがちですが、実は最初の設定を甘くすると、後々の経理や確定申告で大きな手間が発生します。
特に重要なのが 勘定科目 と 消費税設定(免税事業者の場合は不要)です。
この2つを最初に整えておくことで、日々の記帳がスムーズになり、確定申告もラクになります。
1. 勘定科目の設定
勘定科目とは、事業のお金の出入りを分類するための“フォルダ”のようなものです。
例えば、次のように支出や収入を管理してきます。お金の流れを「正しく仕分け」することが目的となります。
- 仕入れ → 「仕入高」
- 文房具やコピー用紙 → 「消耗品費」
- 携帯代やクラウドサービス → 「通信費」



会計ソフトには、一般的な勘定科目が用意されていますが、自分の事業に合わせてカスタマイズすることもできます。 例えば「広告宣伝費」と「SNS広告費」を分けておけば、どの媒体に効果があったか分析しやすくなります。補助科目などを上手に活用することもご検討ください。
なお、財務分析をする上で、期別の勘定科目ごとの比較は大変重要となります。一度決めたら途中でコロコロ変えないことが重要です(継続性が大事)。
2. 消費税の設定
開業したばかりの個人事業主は、原則として 2年間は消費税の免税事業者 です。
ただし、2期前の課税売上が1,000万円を超えるなど、一定の場合に該当することにより、消費税の課税事業者となります(詳しくは別の記事でご説明いたします。)。
また、インボイス制度が開始したことより、取引先から「適格請求書発行事業者(消費税の課税事業者)になってほしい」とお願いされるケースも増えています。「消費税課税事業者選択届出書」提出することにより、開業時から消費税の課税事業者を選択することも可能となります。ただし、消費税課税事業者となることによる税負担や手間は相当なものとなりますので、顧問税理士と相談の上、慎重にご検討ください(税理士が決まっていない場合には、こちらからお気軽にお問い合わせください。)。



余談ですが、消費税課税事業者選択届出書の提出期限は、課税事業者としての適用を受けたい課税期間の初日の前日までとなります。ただし、開業初年度の場合には、その課税期間の末日までに提出すれば、初年度から課税事業者になれます。例えば、令和7年(2025年)に開業した場合、令和7年12月31日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、令和7年分から課税事業者として扱われます。



開業初年度は設備投資を沢山するから、課税事業者を選択することで、その設備投資などにかかった消費税の還付を受けることができる可能もあるんですよね?



そうだね。ただ、一度課税事業者を選択すると、原則2年間は免税事業者に戻れないから、注意が必要です。
(3)請求書・領収書のフォーマット作成
個人事業主として開業したら、すぐに取り組んでほしいのが 「請求書・領収書のフォーマット作成」 です。
「取引が始まってから考えればいいのでは?」と思う方もいますが、実はここを後回しにすると、いざという時に慌ててしまい、信頼を損ねることも…。
1. 請求書フォーマットを整えるメリット
- 信頼感を与えるビジネスの“顔”
請求書は、取引先にとって「あなたの事業の第一印象」とも言える書類です。
フォーマットが整っているだけで、「この人はきちんとしている」という信頼感を与えられます。
- 経理・入金管理がスムーズ
請求書に必要な情報が揃っていれば、入金漏れや金額の食い違いを防げます。
また、会計ソフトやクラウド請求書サービスと連携すれば、自動で売上管理ができるので効率的です。
2. 領収書フォーマットを整えるメリット
- 取引の証拠として必須
領収書は「代金を受け取りました」という証明書です。
税務調査や経理処理の際に必ず必要になるため、正しいフォーマットで発行できる準備が欠かせません。 - インボイス制度への対応
2023年10月から始まったインボイス制度により、適格請求書発行事業者(消費税の課税事業者)は、領収書や請求書に「登録番号」「税率ごとの消費税額」などの記載が求められます。
フォーマットを最初からインボイス対応にしておけば、後に適格請求書発行事業者(消費税の課税事業者)となった場合でも、一部を修正するだけでインボイス要件を充足できることになります。
(4)SNSやホームページでの告知(地域名+業種でSEO効果)
個人事業主として開業したら、まずやっておきたいのが 「自分の存在を知ってもらうこと」。
どんなに良いサービスを用意しても、知ってもらえなければ始まりません。
そのために有効なのが、SNSとホームページでの告知です。
特に「地域名+業種」を意識した発信は、検索エンジン対策(SEO)にも直結し、地元のお客様に見つけてもらいやすくなります。
1. なぜSNSとホームページでの告知が必要なのか?
SNSは「拡散力」
- InstagramやX(旧Twitter)、Facebookは、気軽に情報を発信できる場。
- 写真や日常の一コマを交えて投稿することで、親近感を持ってもらえる。
- フォロワーがシェアしてくれることで、口コミ的に広がる。
ホームページは「信頼の拠点」
- SNSは流れていく情報ですが、ホームページは「24時間営業の名刺」。
- 事業内容・料金・アクセス方法を整理して掲載することで、信頼感がアップ。
- 検索エンジンに拾われることで、新規顧客の流入につながる。
2. 「地域名+業種」でSEO効果を狙う
検索する人は「自分に近い場所」で「必要なサービス」を探しています。
たとえば――
- 「町田市 税理士」
- 「横浜 カフェ モーニング」
- 「新宿 ネイルサロン 個室」
こうした 地域名+業種 の組み合わせは、検索ボリュームは大手に比べて少ないですが、成約率が高い“濃い見込み客”を呼び込めます。
3. 告知の具体的な進め方
- ホームページを立ち上げる
- WordPressやペライチなどでOK。
- 「事業内容」「料金」「プロフィール」「アクセス」を必ず掲載。
- SNSアカウントを開設
- Instagramならビジュアル重視、Xなら速報性重視。
- 開業準備の様子や日常を発信して親近感を演出。
- 地域名+業種を意識した投稿
- 「町田市で開業準備中の税理士です」
- 「横浜でテイクアウト専門のカフェを始めました」
- リンクをつなげる
- SNSプロフィールにホームページURLを掲載
- ホームページにSNSアイコンを設置
6.よくある失敗と回避策
(1)開業届を出し忘れる
失敗例
「とりあえず事業を始めてからでいいや」と思っていたら、開業届を出さないまま数か月経過…。
→ 青色申告の申請もできず、節税メリットを逃してしまう。
回避策
- 退職や開業準備と同時に「開業届」を提出する準備をする。
- 提出期限関係なく、開業と同時に提出する。
(2)青色申告の期限を過ぎる
失敗例
「青色申告はお得らしい」と聞いていたのに、申請期限(開業から2か月以内 or その年の3月15日)を過ぎてしまい、白色申告に…。
回避策
- 開業届と同時に「青色申告承認申請書」も提出する。
- カレンダーやタスク管理アプリで「期限アラート」を設定しておく。
(3)領収書やレシートの保管漏れ
失敗例
「後でまとめればいいや」と思っていたら、レシートが紛失。経費にできず税金が増える…。
回避策
- 受け取ったらすぐに「事業用ファイル」や「封筒」に入れる。
- スマホで撮影してクラウド保存する(電子帳簿保存法対応アプリを使うとベスト)。
- 月ごとに整理する習慣をつける。
(4)事業とプライベートの資金混同
失敗例
個人の口座やカードで事業の支払いをしてしまい、後で仕分けが大混乱。確定申告の時に「これは事業?個人?」と悩む羽目に…。
回避策
- 開業直後に「事業用銀行口座」と「事業用クレジットカード」を必ず作る。
- 売上入金も経費支出もすべて事業用口座に集約する。
- プライベートと事業を分けることで、経理も資金繰りもクリアになる。
7.まとめ
まずは開業届と青色申告承認申請書、この2つを期限内に!
事業を始めたばかりの頃は、事業計画の立案や実務の準備など、やるべきことが山のようにあります。そのため、直接売上に関わらない手続きはつい後回しにしてしまい、気づいたときには期限を過ぎていた…ということも少なくありません。
その気持ちはよくわかります。開業直後は不安も多く、視野が狭くなりがちですし、相談できる相手も限られているため、うっかりミスをしてしまうのも自然なことです。
だからこそ、まずは 「開業届」と「青色申告承認申請書」 この2つを期限内に提出することを意識して、一歩ずつ着実に進んでいきましょう。
せっかくの船出です。どうせなら不安ばかりにとらわれず、この挑戦を楽しみましょう!もちろん、一人で心細くなる瞬間もあるでしょう。そんな時に、気軽に雑談できる“同志”のような存在がいれば、気持ちはぐっと楽になります。
人を雇うほど事業が安定していない時期だからこそ、顧問税理士をつけるのも一つの選択肢です。私は「親しみやすく、良い意味で税理士らしくない税理士」を目指しています。あなたの良き相談相手として、税務のことはもちろん、将来の夢や事業の展望についても一緒に語り合えたら嬉しいです。
まずは無料相談から、気軽にお話ししてみませんか?ご連絡お待ちしております!



開業の手続きだけでもこんなにあるのか・・・
何とか一人でもできそうだけど。



そうだね。一人でも全然対応はできると思います。ただ、未経験の手続きを調べながらやるのは大変です。当然ながら、時間はかかるし、ミスをする確率も増えます。知らず知らずの間に、税金面で損をする可能性だってあります。経営者様は、できる限り事業に専念された方が良いと思いますので、こういった手続きは税理士に頼ってみてはいかがでしょうか?
私は、町田で独立開業したばかりの“挑戦者”です。
だからこそ、これから事業を始める同じ挑戦者の皆さまを心から応援したいと思っています。
その想いを形にするために、特別キャンペーンをご用意しました。
顧問契約を締結いただいたお客様限定で、顧問契約の範囲内に含まれる 開業手続き(青色申告承認申請書や開業届の提出など)を無料でサポート いたします。
開業初年度は不安や手続きの多さに戸惑うこともあると思います。そんな時こそ、税務のことは安心して任せていただき、事業に集中していただければ嬉しいです。詳しくはこちらからお気軽にお問い合わせください。










コメント