
ボス、医療法人の顧問もやったことあるんですよね?



大規模な医療グループから個人まで担当したことありますよ。



私、医療法人についてあまり詳しくなくて、持ち分あり医療法人と持ち分なし医療法人があると聞いたのですが、どういう違いがあるのでしょうか?将来、私が医療法人を設立するとしたらどちらが良いかも教えてください。



…実は、持ち分あり医療法人は、平成18年の医療法改正により2007年(平成19年)4月1日以降設立ができなくなってしまいました。ただ、未だに持ち分あり医療法人は医療法人全体の60%を占めていると言われております。「認定医療法人制度」などを活用して、持分なしへの移行が促進されている状況です。今回は、持ち分あり医療法人と持ち分なし医療法人のそれぞれの基礎知識について、比較表を交えながらわかりやすく解説していきますね。
1.医療法人制度の概要と「持分あり」「持分なし」の違いが注目される背景
医療法人制度における「持分」とは?
医療法人制度を理解するうえで欠かせないキーワードのひとつが「持分(もちぶん)」です。
持分とは、医療法人の出資者(社員)が出資額に応じて有する財産的権利を指します。具体的には、医療法人が解散した際に、出資者が払戻しや残余財産の分配を受けられる権利のことです。
イメージしやすく言えば、株式会社における「株式」に近い存在です。株主が株式を通じて会社に対する権利を持つように、医療法人の出資者も「持分」を通じて法人に対する財産的な権利を持つことになります。
ただし、株式会社と異なり、医療法人は公益性の高い存在であるため、持分の扱いには特有のルールや制限があります。特に「持分あり医療法人」と「持分なし医療法人」では、承継や相続、残余財産の帰属先に大きな違いがあるため、制度理解が欠かせません。
「持分あり」と「持分なし」の歴史的背景
持分あり医療法人の時代
かつて、2006年(平成18年)の医療法改正以前に設立された医療法人は、すべて「持分あり医療法人」でした。出資者(社員)は出資額に応じた財産的権利を持ち、法人解散時には残余財産の分配を受けられる仕組みでした。
これらの法人は現在も存続しており、「経過措置型医療法人」と呼ばれています。
改正の背景と「持分なし医療法人」への移行
しかし、持分あり医療法人には以下のような課題がありました。
- 出資者の死亡に伴い、相続税の課税が発生し、医療法人の資金繰りや医業継続に支障をきたすリスク
- 解散時に残余財産を分配できる仕組みが、非営利性の確保に反するとの指摘
こうした問題を解消するため、国は「非営利性の徹底」と「地域医療の安定性の確保」を目的に制度改革を実施することとし、2007年(平成19年)4月1日以降に新たに設立される医療法人は、すべて「持分なし医療法人」に限定されました。
持分あり医療法人に潜む「相続リスク」とは?
「持分あり医療法人」は、長年の経営を通じて利益や内部留保が積み重なると、その持分の評価額が数億円から数十億円に達するケースも珍しくありません。
この高額な持分は、出資者(理事長など)が亡くなった際に相続財産として課税対象となります。その結果、後継者や家族に莫大な相続税の負担がのしかかり、医療法人の資金繰りや事業継続を直撃するリスクがあります。
さらに深刻なのは、経営に関与していない相続人からの**「払戻請求」リスク**です。持分を相続した親族が「自分の持分を現金で返してほしい」と請求すれば、法人は多額の資金を一括で用意せざるを得ず、経営基盤が一気に揺らぐ可能性があります。
こうした背景から、現在では「持分なし医療法人」への移行が強く推奨されています。持分なしに移行することで、相続税の課税リスクや払戻請求の問題を根本的に回避でき、地域医療の安定的な継続にもつながります。
2.持分あり医療法人とは (概要、メリット、デメリット)
(1).持分あり医療法人の概要
持分あり医療法人(経過措置型医療法人)とは、社員(出資者)が出資額に応じた「持分」という財産的権利を有している医療法人を指します。
出資者である理事長や一族が法人の実質的なオーナーとして運営できる点が特徴です。2007年の医療法改正以降は新設できなくなり、現在は改正前に設立された法人のみが「経過措置型」として存続しています。
(2).持分あり医療法人のメリット
持分あり医療法人のメリット
- 残余財産を受け取れる権利
法人が解散する際、出資比率に応じて残った財産を社員が受け取ることができます。 - 柔軟な経営と承継が可能
一族経営を維持しやすく、経営の自由度が高い傾向にあります。意思決定のスピード感を重視する法人にはメリットとなります。 - M&A(法人売却)の可能性
出資持分を譲渡することで、実質的に法人を売却することが可能です。医療法人の承継手段として活用されるケースもあります。
(3).持分あり医療法人のデメリット
持分あり医療法人は、特に事業承継や資金流出リスクに大きな課題を抱えています。
- 莫大な相続税の負担
持分は相続財産として評価され、その額が数億円〜数十億円に達することもあります。後継者が相続税を支払う資金を確保できない場合、経営継続が困難になるリスクがあります。 - 高額な払戻請求リスク
出資者が退職・死亡した場合、本人や相続人はその時点での「時価純資産価額」に基づき払戻請求を行うことが可能です。これにより、法人が予期せぬ巨額の資金流出を強いられ、財務基盤が不安定になる恐れがあります。 - 贈与税の発生リスク
他の出資者への贈与税:一部の出資者が持分を放棄すると、残りの出資者の持分価値が上昇し、その上昇分に贈与税が課税されます。
医療法人への贈与税:出資者全員が持分を放棄した場合、医療法人自体が贈与を受けたものとみなされ、贈与税が課税されるケースがあります。 - 遺留分のリスク
持分の評価額が高額になると、他の財産とのバランスが崩れ、後継者ではない相続人から遺留分(最低限取得できる財産の権利)を請求される可能性があります。その結果、後継者が多額の現金を支払わざるを得なくなるケースもあります。
3. 持分なし医療法人とは (概要、メリット、デメリット)
(1).持分なし医療法人の概要
持分なし医療法人とは、社員(出資者)が法人に対して「持分(財産的権利)」を持たない医療法人社団のことです。
2007年(平成19年)4月1日の医療法改正以降、新たに設立される医療法人はすべてこの形式に限定されています。
さらに、この中で「基金制度」を採用しているものは基金拠出型医療法人と呼ばれます。これは、拠出者に対して拠出額を返還する義務を法人が負う仕組みであり、持分制度の代替として位置づけられています。
(2).持分なし医療法人のメリット
(2) 持分なし医療法人のメリット
- 相続税リスクの回避(事業承継がスムーズ)
内部留保された資産(基金相当額を除く)は持分が存在しないため、相続税の課税対象外となります。これにより、理事長の逝去時にも後継者が莫大な相続税を負担する必要がなく、事業承継を円滑に進められます。 - 払戻請求リスクの回避
出資者や退職者は、法人の純資産に基づく払戻しを請求できません。基金拠出型の場合でも返還されるのは拠出額のみであり、高額な時価純資産に基づく請求リスクを回避できます。 - 税務上の優遇措置
・法人税と所得税の税率差を活用した節税効果
・役員給与に対する給与所得控除の適用
・家族従業員への給与支給による所得分散(累進課税の軽減)
・役員退職給与の支給(適正額は損金算入可能) - 経営の柔軟性(事業拡大が可能)
・分院の開設(常勤医師は理事就任が必要)
・介護老人保健施設や訪問看護ステーションなど、付帯業務の展開が可能 - キャッシュフローの改善
社会保険診療報酬支払基金からの入金時に源泉徴収が行われないため、毎月のキャッシュフローがスムーズになります。
(3).持分なし医療法人のデメリット
- 残余財産が国等に帰属
解散時には、拠出者に返還すべき基金相当額を除き、残余財産は国や地方公共団体等に帰属します。 - 経営の自由度が低い
非営利性・公共性が強調されるため、資産の私有性は低く、理事の選任なども理事会や評議員会の承認が必要。承継の自由度は持分あり法人に比べて制約されます。 - 法人売却(M&A)ができない
出資持分が存在しないため、持分譲渡による法人売却は不可能です。 - 交際費の損金不算入制度
医療法人が支出する接待交際費には損金不算入制度が適用され、法人税務上の制約があります。
4. 両者の比較表
| 項目 | 持分あり医療法人 | 持分なし医療法人 |
|---|---|---|
| 設立 | 2007年4月以降、新設不可 (既存の経過措置型のみ) | 新設可能 |
| 出資者の権利 | あり (出資比率に応じた払戻し/分配権) | なし (基金拠出型は基金の返還権のみ) |
| 相続税 | 持分が相続財産として 課税対象となる | 持分が存在しないため 相続税の課税対象外 (基金拠出型は基金のみ課税対象) |
| 解散時の財産 | 出資比率に応じて出資者に分配 出資額を超える部分は「配当」とみなされ、所得税課税される場合あり | 国や公共機関に帰属する (基金拠出分を除く) |
| 退職時の払戻請求 | 時価純資産価額に基づく 高額な請求リスクあり | 基金相当額のみ返還 (基金拠出型の場合) |
| 資産の私有性 | 高い(オーナー的運営が可能) | 低い (非営利・公共性が強調される) |
| 事業承継の自由度 | 高い(親族内承継しやすい) | 低い(理事会などの関与が必要) |
5. 実務上のポイント:移行を検討すべきタイミングと対策
「持分あり医療法人」を経営されている方にとって最大の課題は、いかに税負担を回避し、安定的に「持分なし医療法人」へ移行するかという点です。ここでは、実務上押さえておくべき制度と対策を整理します。
認定医療法人制度の活用
従来、持分あり医療法人から持分なし医療法人へ移行する際には、持分放棄によって医療法人に「みなし贈与税」が課されるという大きなハードルがありました。
この問題を解消するために設けられたのが、「認定医療法人制度」です。厚生労働大臣の認定を受けることで、税負担を回避しながら持分なし医療法人へ移行できる税制優遇措置が用意されています。
認定医療法人制度の優遇措置
- みなし贈与税の非課税:移行時に医療法人へ課される贈与税が非課税となる。
- 相続税の納税猶予・免除:出資者の相続人にかかる相続税が猶予され、最終的に持分なしへ移行すれば免除される。
- 贈与税の非課税:出資者間での持分移転に伴う贈与税も非課税となる。
制度の期限と移行期間の緩和
- 期限延長:この制度は恒久措置ではなく期限付きですが、令和5年度税制改正により、認定を受けられる期限は 令和8年12月31日まで延長 されました。
- 移行期間の緩和:認定を受けてから移行を完了するまでの期間は、従来の3年以内から 5年以内 に緩和されています。
認定を受けるための要件
認定を受けるには、法人運営に関する厳格な要件を満たす必要があります。代表的なものは以下のとおりです。
- 社会保険診療報酬に係る収入が全体の 8割超 であること
- 役員報酬が不当に高額でないこと
- 公益性・非営利性を確保するための運営体制を整備していること
さらに、移行後も 6年間のモニタリング期間 が設けられ、適正な運営が継続されているかチェックされます。
移行が難しい場合の対策
認定医療法人制度の要件を満たせない、または「解散して財産を受け取りたい」など移行に抵抗がある場合には、持分あり法人のリスクを軽減する対策が必要です。
生命保険を活用した資金確保
相続税の納税資金や将来の払戻請求に備えるため、生命保険の活用は有効です。出資者(被保険者)の死亡時に後継者(受取人)へ現金が入る設計や、法人に保険金が入り死亡退職金の原資とする仕組みを整えることが推奨されます。
持分の評価引き下げ
高額な持分の評価額を下げるため、適正な役員退職金の支払いや、損金算入される保険の活用、含み損がある資産の売却などを検討、実行することで、相続税や払戻請求リスクを軽減できます。
6. まとめ
持分あり医療法人は、オーナーシップが高いというメリットがある一方で、相続や払戻請求による多大なリスクを常に抱えています。特に、法人が成長し、純資産が増えるほど、そのリスクは増大します。
将来、後継者に「納税」という負の遺産を残さないためにも、現状の持分評価額や、相続発生時の納税予測額を早めに把握し、認定医療法人制度の活用を含めて対策を講じる必要があります。
認定医療法人制度は複雑な要件と手続きを伴います。円滑な事業承継とリスク回避のためにも、医療法人の事業承継に特化した専門の税理士に相談することを強くおすすめします。



それぞれメリットデメリットありますね。これは悩みます。持ち分なしが推奨されているとはいえ、頑張って積み上げてきた資産(残余財産)が解散することにより国や地方公共団体等に帰属するのはなんとも。。。



一概にどちらが良いとは言えませんよね。まずは将来の着地点をしっかりとイメージしてから、それに合う方法を選択すべきだと思います。そのためには、現状の財務状況の把握や、後継者の選定は早い段階で行うべきだと考えております。医療法人は株式会社と異なり、税務の面でも特殊な取り扱いが多数あり、医療法人の仕組みを理解していない税理士も多くいます。税理士選定にお困りの医療経営者様は、お気軽にこちらにお問い合わせください。

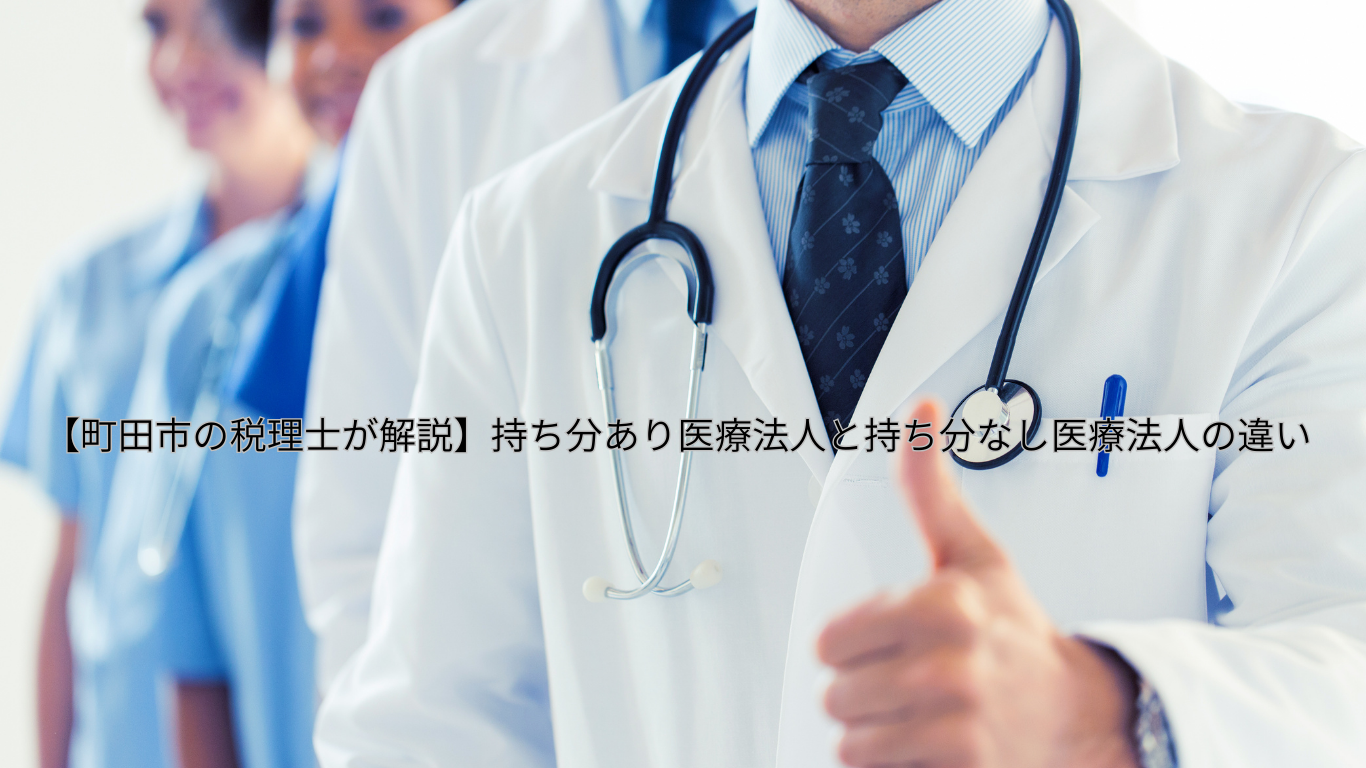








コメント