
ボス!税金を減らす方法として、沢山寄附金を支出するのはどうですか?世のため人のためにもなりますし、所得も圧縮できますし、一石二鳥ですよね!



実は、寄附金の内容にもよりますが、基本的には、支出した寄附金のうち、一部しか損金に算入できないのです。寄附金が一部しか損金に算入できない理由としては、法人の恣意的な支出による課税の不公平を防ぐためです。



恣意的な支出、、、課税の不公平、、、?



寄附金は「事業に直接必要な支出」ではなく、会社の好意や社会貢献のために出すお金です。
もし寄附金を全部経費にできてしまうと、極端な話「寄附を増やせば税金をほとんど払わなくて済む」という不公平な状況が生まれてしまいます。
そのため税法では、損金算入に制限を設けているのです。
一方で、国や地方公共団体、学校法人、社会福祉法人など、公益性の高い団体への寄附金は社会全体に役立つ支出と位置づけられています。こうした寄附については、社会貢献の色合いが強いことから、全額損金算入または特別枠での損金算入が認められるなど、優遇措置が設けられています。
寄附金の損金不算入制度を正しく理解していないと、知らないうちに過少申告や税務リスクにつながる可能性もあります。本記事では、寄附金の範囲から損金算入限度額の計算方法まで、最新の制度をわかりやすく解説します。
1. 寄附金の損金不算入制度の概要
企業が社会貢献や地域支援の一環として寄附を行うことは素晴らしい取り組みです。しかし、法人税の計算においては、寄附金は「事業の収益獲得に直接必要な支出」ではないとされるため、課税の公平を保つ観点から損金算入に一定の制限が設けられています。
この「寄附金の損金不算入制度」を正しく理解し、寄附金の種類や損金算入限度額の計算を誤らなければ、想定外の税負担を回避することができます。逆に、制度を理解せずに処理してしまうと、税務調査で否認されるリスクや、過少申告につながる可能性もあるため注意が必要です。
本記事では、
- 法人税法上の寄附金の定義
- 寄附先ごとの損金算入の取扱い
- 実務で押さえておくべき留意点
を、町田市の税理士がわかりやすく解説します。



個人が寄附した場合の税務上の取り扱いを知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
2.寄附金の定義
(1)法人税法上の寄附金の範囲
法人税法における「寄附金」とは、
法人が金銭・物品・その他の経済的利益を、反対給付を求めずに無償で提供することを指します。
ここで重要なのは、名目にかかわらず寄附金とみなされるという点です。
たとえば「寄附金」「拠出金」「見舞金」など、呼び方が異なっていても、実態が「無償の供与」であれば寄附金として扱われます。
寄附金の額は、
- 金銭の場合 → その支出額
- 金銭以外の資産や経済的利益の場合 → 贈与や供与を行った時点の時価
で評価されます。
(2)寄附金に含まれないもの
寄附金名義で支出していても、実態が他の費用に当たる場合は「寄附金」から除外されます。名称ではなく、反対給付の有無や目的で判定するのが原則です。
特に区別が必要なのは以下の費用です。
- 役員の私的負担すべき支出
役員個人の私的な支出を会社が負担した場合は、寄附金ではなく役員給与(または賞与)として取り扱われます。
- 交際費・接待費・福利厚生費
取引先への接待や贈答、従業員の慰安・福利目的の支出は、寄附金ではなく各費用として処理します。
- 広告宣伝費・見本品等
不特定多数への認知向上や販売促進を目的とする支出(例:カレンダー・ノベルティ配布、試供品の提供)は広告宣伝費や販売促進費として扱います。
したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのか、それとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。



重要なのは「名目より実態」。同じ“寄附”でも、営業促進や福利目的なら寄附金扱いにはなりませんので、ご注意ください。
3.寄附金の区分と取扱い
(1)一般の寄附金(下記以外の寄附)
下記(3)や(4)そして指定寄附金(財務大臣が指定したもの)などに該当しない寄附金は、一般の寄附金として取り扱われます。
政治団体、寺社、町内会などへの寄附金がこれに該当します。一般の寄附金は、後述の計算方法により算出される損金算入限度額を超えた部分が損金不算入となります。



最も幅広く該当するのが「一般寄附金」であり、実務上は限度額計算が必須です。
(2)完全支配関係がある他の法人に対する寄附金
内国法人が、その内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る)がある他の内国法人に対して支出した寄附金は、その全額が損金不算入となります。
これは、グループ内部の寄附・受贈について課税関係を生じさせないという趣旨によるものであり、寄附を受けた側(受贈法人)では、原則としてその受贈益の全額が益金不算入とされます。
なお、親会社と子会社との間に個人による完全支配関係も同時に存在する場合であっても、法人による完全支配関係がある限り、この全額損金不算入の規定が適用されます。
(3)国または地方公共団体(以下「国等」といいます。)に対する寄附金
国や地方公共団体(都道府県、市区町村、特別区など)に対する寄附金は、その公共性の高さから、全額が損金に算入されます。
典型例としては、公立高校の施設の新築費用や、公立図書館の図書購入費などが挙げられます。ただし、「国」や「地方公共団体」は日本国の団体を指すため、外国政府や外国の州への寄附金はこれに該当しません。
(4)特定公益増進法人に対する寄附金(学校法人・社会福祉法人・赤十字社など)
特定公益増進法人とは、教育や科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献など、公益の増進に著しく寄与する法人として政令で定められた団体をいいます。
具体的には、学校法人、社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人などが該当します。
特定公益増進法人に対する寄附金は、一般の寄附金とは別枠で損金算入限度額(特別損金算入限度額)が設けられており、その範囲内で損金算入が認められます。この特別限度額を超える金額は、後述する一般の寄附金の損金算入限度額の範囲内でさらに損金算入が可能です。



社会的意義の高い寄附は、優遇的に扱われる仕組みです。
(5)国外関連者に対する寄附金
法人が国外関連者(50%以上の株式保有関係や実質的支配関係がある外国法人など)に対して支出した寄附金の額は、全額が損金不算入となります。これは租税特別措置法に規定されています。



国外関連者への寄附は、租税回避防止の観点から厳格に制限されています。
(6)特定公益信託に対する支出金
公益信託のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして財務大臣が指定した寄附金(指定寄附金)であれば、全額が損金に算入されます。
(7)寄附金の区分と損金算入の取り扱い(まとめ表)
上記(1)から(6)を表にまとめると以下のようになります。
| 区分 | 損金算入の取扱い | 根拠条文等 |
|---|---|---|
| (1) 一般の寄附金 | 損金算入限度額を超えた 部分が損金不算入 | 法法37条1項 |
| (2) 完全支配関係がある 他の法人に対する寄附金 | 全額損金不算入 | 法法37条2項 |
| (3) 国または地方公共団体等 に対する寄附金 | 全額損金算入 | 法法37条3項1号 |
| (4) 特定公益増進法人 に対する寄附金 | 一般の寄附金とは別枠で 特別損金算入限度額まで損金算入 | 法法37条4項 |
| (5) 国外関連者に対する寄附金 | 全額損金不算入 | 措法66条の4第3項 |
| (6) 特定公益信託に対する支出金 | 全額損金算入 (指定寄附金) | 法法37条3項2号 |
4. 寄附金の損金算入限度額の計算方法
全額損金算入または全額損金不算入となる寄附金(国等、完全支配関係法人、国外関連者への寄附金)を除き、損金算入が制限される寄附金には、一般の寄附金と特定公益増進法人に対する寄附金があります。
これらの損金算入限度額は、法人の規模や所得金額に応じて計算されます。それぞれの計算式は次の通りとなります。
(1)一般の寄附金
①寄附金を支出する法人が普通法人、一定の労働者協同組合、協同組合等および人格のない社団等(下記②に掲げるものを除きます。)の場合
〔損金算入限度額〕=
〔(期末の資本金の額+資本準備金の額or出資金の額)×当期月数/12×0.25%+所得の金額×2.5%〕×4分の1
②寄附金を支出する法人が普通法人、協同組合等および人格のない社団等のうち資本または出資を有しないもの(法人課税信託に係る受託法人を含みます。)、非営利型の一般社団法人および一般財団法人ならびにNPO法人(認定NPO法人を除きます。)などのみなし公益法人等の場合
〔損金算入限度額〕=〔所得の金額×1.25%〕
国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm
(2)特定公益増進法人に対する寄附金(学校法人・社会福祉法人・赤十字社など)
①寄附金を支出する法人が普通法人、一定の労働者協同組合、協同組合等および人格のない社団等(下記②に掲げるものを除きます。)の場合
〔特別損金算入限度額〕=
〔(期末の資本金の額+資本準備金の額or出資金の額)×当期月数/12×0.375%+所得の金額×6.25%〕×2分の1
②寄附金を支出する法人が普通法人、協同組合等および人格のない社団等のうち資本または出資を有しないもの(法人課税信託に係る受託法人を含みます。)、非営利型の一般社団法人および一般財団法人ならびにNPO法人(認定NPO法人を除きます。)などのみなし公益法人等の場合
〔特別損金算入限度額〕=〔所得の金額×6.25%〕
国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm
5. 寄附金経理の実務上の留意点
(1)寄附金と広告宣伝費・交際費の区分が重要(税務調査でよく指摘される)
寄附金と、広告宣伝費や交際費は、金銭や物品を贈与する点で近接しており、税務調査においてもその区分の適否がよく指摘されます。
交際費等は、得意先や仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用を指します。
一方、寄附金は、基本的に事業に直接関係のない者に対する金銭の贈与や、反対給付のない支出と判断されます。
判断は個々の実態によりますが、例えば、事業に直接関係のない社会事業団体や政治団体への拠金、神社の祭礼等の寄贈金などは、原則として寄附金に該当し、交際費等には含まれません。
企業の支出が「広告宣伝費」として全額損金算入されるか、「交際費」として一定の損金不算入の対象となるか、「寄附金」として限度額規制の対象となるかは、税負担に直結するため、慎重な検討が必要です。



企業の支出が「広告宣伝費」として全額損金算入できるのか、「交際費」として一部制限を受けるのか、「寄附金」として限度額規制の対象になるのかは、税負担に直結するため慎重な判断が必要です。判断が難しいだけに、税務調査でも、チェックされるポイントの一つですので、不安な場合には、顧問税理士に相談してください。
(2)企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)は税額控除も可能
地方公共団体の地方創生事業に対する企業からの寄附を促進するための制度として、企業版ふるさと納税(正式名称:地方創生応援税制)があります。
この制度を活用すると、企業は寄附金額の最大約9割の税軽減効果(法人関係税)を受けることができ、企業の実質的な負担を1割まで圧縮できます。
税軽減の仕組みは、従来の寄附金と同様の損金算入(約3割)税額控除(約6割)令和9年度まで延長されています。
ただし、以下の点に留意が必要です。
• 本社が所在する地方公共団体(自治体)への寄附は対象外です。
• 寄附の代償として経済的な利益(返礼品、補助金、有利な貸付など)を受け取ることは禁止されています。企業のPR効果(自治体ホームページへの企業名掲載など)は認められています。



ちなみに、企業版ふるさと納税は返礼品はありませんので、ご注意ください。



地方税やそれぞれの限度額との兼ね合いもあるため、寄附する際には慎重な判断が求められます。別表の作成や計算も結構複雑で大変です。検討されている場合には、顧問税理士に相談されることをお勧めします。
(3)記録保存の徹底(寄附先・金額・趣旨を明確に)
寄附金について損金算入の規定の適用を受けるためには、必要な手続きと記録保存が義務付けられています。
特に、特定公益増進法人や認定NPO法人等に対する寄附金について、別枠の損金算入を適用する場合、寄附金を支出した事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表14(2))を添付し、その寄附金が法人の主たる目的である業務に関連するものであることを寄附先法人が証する書類などを保存しておく必要があります。
また、企業版ふるさと納税を適用する場合にも、寄附決済完了後に自治体より発行される「寄附受領証明書」を用いて経理処理を行う必要があります。



書類不備は税務調査で否認されるリスクが高いため、寄附先・金額・趣旨を明確に記録し、証憑を必ず保存しましょう。
6. まとめ
法人が支出する寄附金の税務上の取扱いについて、最も重要なのは、寄附先の区分に応じた正しい処理を行うことです。
• 国等や指定寄附金は全額損金算入。
• 完全支配関係法人や国外関連者へは原則全額損金不算入。
• 特定公益増進法人と一般の寄附金には、それぞれ異なる損金算入限度額が設けられています。
特に企業版ふるさと納税のように、高い税制優遇を受けられる制度も存在しますが、適用要件や手続き、他の費用(交際費等)との区別には専門的な判断が伴います。企業の社会的貢献と財務健全性を両立させるためにも、寄附の計画段階から税理士と相談し、正確な税務処理を徹底しましょう。



寄附金の損金不算入制度について、理解ができました!寄附金の区分判定が難しそうですね。



そうですね。同じ寄附先でも、用途によって、寄附金の区分が変わることもあるため、複数寄附されている場合には、税理士に相談された方が良いと思います。
また、「せっかく寄附をしても損金不算入になるくらいなら…」と躊躇してしまう方も少なくありません。ですが、年度末が近づけば、会社の所得の着地点がある程度見えてきます。そのタイミングで顧問税理士に依頼し、損金算入限度額の範囲内で寄附金をいくらまで支出できるかをシミュレーションしてもらうのは有効な方法です。相談できる税理士がいない場合には、お気軽にこちらまでお問い合わせください。



個人が寄附した場合の税務上の取り扱いは、こちらの記事をご覧ください。
【町田市の税理士が解説】「所得控除?」「税額控除?」個人が寄附した場合の税務上の取り扱いについて

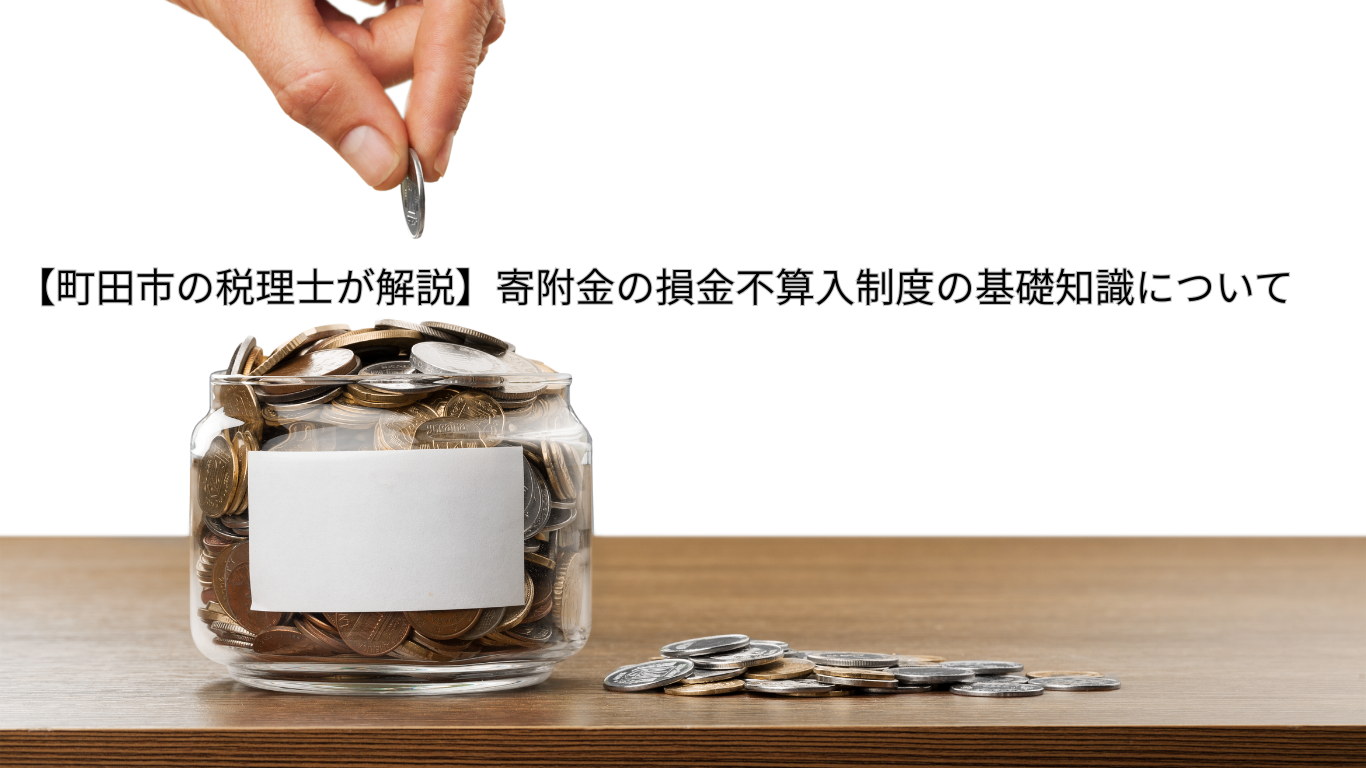








コメント