 ミミレイドン
ミミレイドンボス、年末調整シリーズ2回終わって、次は、基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書(いわゆる基・配・所)の記入方法を教えていただく予定でしたが、実は、令和7年税制改正で新たに追加された特定親族特別控除についてよくわからなくて、、、、



確かに分かりにくい制度ですよね。元々あった特定扶養控除との位置づけとか。それに、いわゆる基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書に、今年から、特定親族特別控除の欄が追加されたのです。なので、今後はいわゆる基・配・特・所へと変わります。



それなら、なおさら特定親族特別控除について詳しく知っておかないといけないのですね。



わかりました。それでは、基礎・配偶者・特別親族特別控除・所得金額調整控除申告書(いわゆる基・配・特・所)の記載例を解説する前に、令和7年税制改正で新たに追加された特定親族特別控除について、わかりやすく解説します。大学生(19歳から22歳)の子を持つ親御さん必見です!
令和7年税制改正で新設された「特定親族特別控除」
日本の報道ではあまり大きく取り上げられていませんが、令和7年税制改正で「特定親族特別控除」という新たな制度が創設されました。新たに創設された「特定親族特別控除」は、大学生年代のお子さんを持つ親御さんに対する扶養控除制度の改正です。
今回はこの制度の内容を、扶養控除との関係や背景も含めて詳しく解説します。
従来の扶養控除と問題点
従来から、19歳以上23歳未満の子ども(いわゆる「特定扶養親族」)を扶養している場合、所得税の控除額として63万円が適用される制度がありました。しかし、この制度では、子どもがアルバイトなどで年間収入が103万円(所得48万円)を超えると、扶養親族の要件から外れ、控除額が一気にゼロになるという仕組みでした。
なお、この「103万円の壁」は、令和7年から給与所得控除および基礎控除の引き上げにより、123万円(所得58万円)に変更されます。
このように、一定の収入を超えると控除が突然なくなる制度設計は、最低賃金の上昇が続く昨今の状況において、学生の就労意欲を削ぐ要因となり、特に年末の繁忙期にアルバイト人材が不足するなどの社会的な弊害が指摘されていました。
また、少子化対策の観点からも、子育て世帯への支援強化が求められておりました。
新設された「特定親族特別控除」とは?対象者の要件は?
こうした背景を踏まえ、年収123万円を超えても控除が段階的に減少する仕組み として導入されたのが「特定親族特別控除」です。控除額が段階的に減少する仕組みは、配偶者控除・配偶者特別控除の仕組みをイメージしていただければと思います。
次に、「特定親族特別控除」の対象となる親族について見ていきましょう。
この制度の対象となるのは、12月31日時点で19歳以上22歳以下の親族で、かつ納税者と同居していることが条件です。対象年齢は大学生に該当する年代ですが、必ずしも大学に在籍している必要はありません。たとえば、浪人中で大学に通っていない場合でも、年齢が条件を満たしていれば対象となります。
なお、配偶者については、すでに配偶者専用の控除制度があるため、この制度の対象外です。また、個人事業主が家族を青色事業専従者として雇用し、給与を支払っている場合、その親族も対象外となります。
対象となる親族の年間収入(給与収入換算)は、123万円超〜188万円以下である必要があります。控除額は、親族本人の収入額に応じて段階的に決定され、申告者(親)の所得やその他の条件は影響しません。つまり、控除額の判定は親族の収入のみを基準とするシンプルな仕組みとなっています。
(配偶者特別控除は配偶者のみならず申告する本人の年収も加味した上で控除額が決まる複雑な仕組みになっていました(申告する本人の所得が1000万円以下)。特定親族特別控除は対象となる親族(大学生)の年収のみで控除額が決まる仕組みになっていますので、親の所得制限はありません。)
対象要件まとめ
- 対象は 19歳以上23歳未満の親族(大学生に多い年齢層ですが、大学生でなくても対象となります。)
- 配偶者は対象外(配偶者控除の仕組みがあるため)
- 青色事業専従者給与を受けている場合は対象外
- 控除額は 親族本人の年収のみで判定(納税者本人(親)の所得制限はなし)
控除額の仕組みと節税効果のイメージ
次に、年収に応じた控除額の決まり方について見ていきましょう。
以下の表は、対象となる特定親族の年収に応じて、申告者(親)が受けられる扶養控除額と、その控除による概算の節税効果を示したものです。
まず、年収が123万円以下の場合は、従来の扶養控除制度に基づき「特定扶養親族」として認定されるため、満額の63万円の控除が適用されます。つまり、今回新設された「特定親族特別控除」は、年収が123万円を超えるケースに対する救済措置として位置づけられています。
この新制度では、年収が150万円以下であれば、従来と同様に63万円の控除が受けられます。控除額が段階的に減少するのは、年収が150万円を超えた場合からです。
具体的には、年収が180万円以下までは、5万円刻みで年収が増えるごとに、控除額が10万円ずつ減少していきます。そして、年収が188万円を超えると制度の適用外となり、控除額はゼロになります。
なお、節税額の概算は、所得税率20%、住民税率10%と仮定して計算しています。たとえば、控除額が63万円の場合、節税効果は約18万9千円にもなり、家計にとって非常に大きなインパクトがある制度と言えるでしょう。
- 年収123万円以下 → 従来どおり特定扶養親族として 63万円控除
- 年収123万円超~150万円以下 → 依然として 63万円控除
- 年収150万円超~188万円以下 → 5万円刻みで控除額が10万円ずつ減少
- 年収188万円超 → 控除なし
| 制度 | 年収(給与収入ベース) | 控除額(扶養控除) | 節税目安※ |
|---|---|---|---|
| 従来の特定扶養控除 | 123万円以下 | 63万円 | 18.9万円 |
| 特定親族特別控除 | 123万円超~ 150万円以下 | 63万円 | 18.9万円 |
| 150万円超~ 155万円以下 | 61万円 | 18.3万円 | |
| 155万円超~ 160万円以下 | 51万円 | 15.3万円 | |
| 160万円超~ 165万円以下 | 41万円 | 12.3万円 | |
| 165万円超~ 170万円以下 | 31万円 | 9.3万円 | |
| 170万円超~ 175万円以下 | 21万円 | 6.3万円 | |
| 175万円超~ 180万円以下 | 11万円 | 3.3万円 | |
| 180万円超~ 185万円以下 | 6万円 | 1.8万円 | |
| 185万円超~ 188万円以下 | 3万円 | 0.9万円 | |
| 対象外 | 188万円超 | 控除なし | 0円 |
※親の税率が所得税20%、住民税10%の場合の概算額となります。親の税金が安くなるということです。
社会保険との関係(19歳以上23歳未満)
社会保険の扶養認定基準に関しても、2025年10月以降、新たなルールが設けられました。
特定親族特別控除(税制)と足並みを揃えるように、19歳以上23歳未満の人の社会保険適用対象が、従来の年収130万円から150万円以上に引き上げられました。これにより、大学生世代のアルバイト収入については、所得税(扶養)の壁も社会保険の壁も150万円に統一されましたので、心置きなく、150万円までアルバイトできることとなりました!



通常、所得税と社会保険の壁はバラバラですが、19歳以上23歳未満に限っては、壁が統一されました!この流れで、配偶者についても、社会保険の壁を160万円まで上げて足並みを揃えてほしいところです。
まとめ:特定親族特別控除
特定親族特別控除の記事のまとめ。
- 特定親族特別控除は、大学生世代の働き控えを防ぐための新制度
- 年収123万円を超えても、段階的に控除が減る仕組みで最大63万円控除
- 親の所得制限はなく、対象は19歳以上23歳未満の親族
- 19歳以上23歳未満に限っては、社会保険の壁も150万円に大幅アップ
今回の制度改正により、子どもがアルバイトに励んでも、扶養控除が突然ゼロになることなく、段階的に減額される仕組みとなった点は、非常に前向きな改善だといえるでしょう。
とはいえ、一定の年収を超えると控除が完全に適用外となる点は従来と変わらず、子どもを扶養する親御さんにとっては、依然として悩ましい部分が残ります。
親としては、子どもには学業に専念してほしいという思いがある一方で、家計への負担も大きいため、ある程度はアルバイトで自分の生活費を賄ってほしいというのが本音ではないでしょうか。
今回の改正によって、税制上の「扶養控除の壁」とともに、社会保険の扶養基準もは緩和されたことは、非常に前向きにとらえるべきだと思います。今後は、さらに税制と社会保険の制度が連動していくことに期待をして、もう少しわかりやすく、また、整合性のある制度設計を期待したいところです。

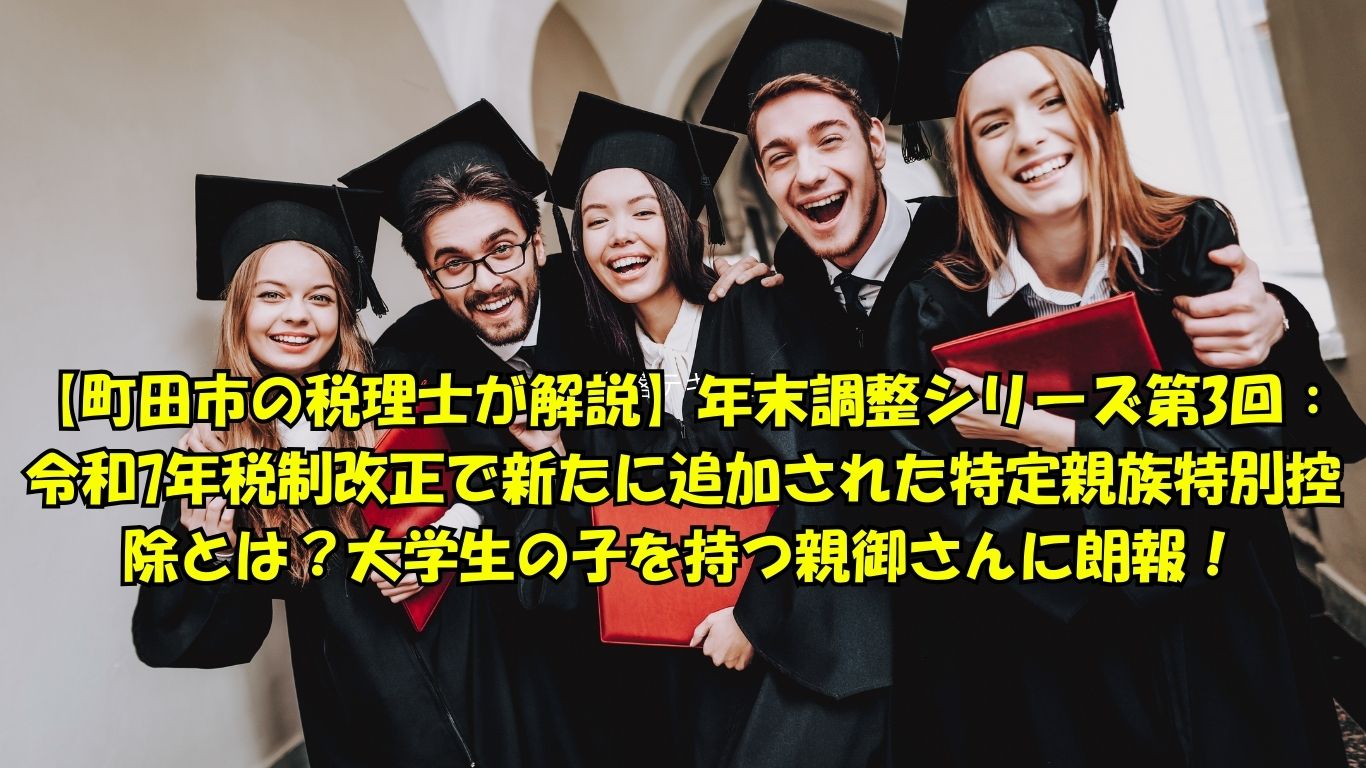








コメント