
昨日は、特定親族特別控除について、よく理解できました!
他の年末調整に影響のある令和7年度改正論点も知りたいです!



令和7年度改正では、前回解説した特定親族特別控除だけでなく、基礎控除や給与所得控除など、今までの常識が覆されるような複雑な改正が多いから、年末調整の実務担当者だけでなく、一般の方も理解しておいた方が良いですからね。それでは、今回は年末調整に影響がある令和7年度税制改正について、わかりやすく解説します。



特定親族特別控除については、こちらの記事もご覧ください。
【町田市の税理士が解説】年末調整シリーズ第3回: 令和7年税制改正で新たに追加された特定親族特別控除とは?大学生の子を持つ親御さんに朗報!
1.はじめに
なぜ令和7年度改正が注目されているのか
令和7年度(2025年度)の税制改正は、年末調整に直結する大きな変更が盛り込まれています。今回の税制改正の基本方針は、「物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応」と「子育て世代への支援強化」です。
物価高が続く中で生活費の負担は増しています。その一方で、パートやアルバイトで働く人々が「税金や社会保険料で手取りが減るから」と、あえて働く時間を抑える現象が広がっていました。これがいわゆる 「就業調整(働き控え)」 です。
今回の改正は、この働き控えを解消し、安心して働ける環境を整えることを目的としています。特に「103万円の壁」と呼ばれてきた収入制限が見直され、「123万円の壁」「160万円の壁」といった新しい基準が導入されることは、日本の労働市場にとって大きな転換点となります。
「103万円の壁」という日本の労働市場の常識が大きく塗り替えられるため、多くの関心を集めているのです。
一方で、制度が複雑化しており、実務の現場は大混乱になると予想されております。
本記事でわかること(対象読者:給与所得者・大学生の親・事業主)
この記事では、令和7年分(2025年分)の年末調整に影響する改正点を、対象読者ごとに整理して解説します。
給与所得者の方へ
- あなた自身の税金が非課税になる「160万円の壁」とは?
- 控除が増えることで手取りがどう変わるのか?
大学生の親御さんへ
- お子さんのアルバイト収入が増えても扶養控除がゼロにならない!
- 新設された 「特定親族特別控除」 の仕組みと節税効果
•事業主・人事労務担当者の方へ
- 年末調整書類の様式変更点
- 実務で絶対に間違えてはいけない注意ポイント



令和7年度改正のポイントを正しく理解し、給与所得者・親御さん・事業主それぞれが 「何をすべきか」 を明確に把握できるように、税理士の視点から、制度の背景と実務対応をわかりやすく解説していきます。
2.改正の背景と目的
最低賃金の上昇と「収入の壁」問題
これまでの税制では、年収103万円を超えると「自分に所得税がかかるライン」であり、同時に「親の扶養控除が外れるライン」でもありました。これが有名な 「103万円の壁」 です。
しかし、最低賃金が年々上昇する中で、この103万円という上限は現実に合わなくなり、特にパート従業員や学生アルバイトにとって「これ以上働くと損をする」という心理的なブレーキになっていました。
今回の改正では、基礎控除や給与所得控除の見直しにより、所得税がかからないラインが実質的に 「160万円」 まで引き上げられます。これにより、働き控えを緩和し、人手不足の解消につなげる狙いがあります。
ただし注意点として、税制上の壁が緩和されても、社会保険の壁(106万円・130万円(NEW150万円)) は依然として存在します。つまり「160万円まで稼げば安心」というわけではなく、税と社会保険は別の制度であることを理解しておく必要があります。
少子化対策としての扶養控除見直し
今回の改正は、単なる「働き控え対策」にとどまらず、子育て世代への支援強化も大きな目的です。
特に19歳から23歳未満の大学生年代の子ども(特定扶養親族)は、親の税負担を軽減するために 63万円の扶養控除 が適用されていました。ところが、子どもの年収が103万円(所得48万円)を超えると、この控除が一気にゼロになってしまう仕組みでした。
その結果、「学費や生活費のためにアルバイトを頑張ると、かえって親の税金が増える」という逆転現象が起き、学生がアルバイトを控える実態につながっていました。
この問題を解消するために新設されたのが、「特定親族特別控除」 です。大学生世代の子どもが一定の収入を得ても、親の扶養控除が段階的に減る仕組みに変わり、急激な税負担増を避けられるようになりました。
3.令和7年度の主な改正ポイント(年末調整に影響するもの)
ここからは、2025年(令和7年分)の年末調整で特に重要となる税制改正のポイントを整理して解説します。これらの改正は、原則として令和7年分以後の所得税に適用されます。
基礎控除の変更
基礎控除は、すべての納税者に適用される「最低限の非課税枠」です。今回の改正で、その金額が大きく見直されました。
• 改正前: 一律48万円
• 改正後(時限措置含む): 合計所得金額に応じて、最大95万円まで引き上げられます。
例えば、年収約200万円以下(合計所得金額132万円以下) の従業員は、基礎控除額が最大95万円に増額されます。一方で、年収が高くなるにつれて控除額は段階的に縮小し、年収850万円超では58万円、さらに合計所得金額2,350万円超では控除ゼロとなります。
| 合計所得金額 (給与額面収入) | 改正前 | 改正後 (令和7・令和8年) | 改正後 (令和9年~) |
|---|---|---|---|
| ~132万円以下 (200万3,999円以下) | 48万円 | 95万円 | |
| 132万円超~336万円以下 (200万3,999円超 ~475万1,999円以下) | 88万円 | 58万円 | |
| 336万円超~489万円以下 (475万1,999円超 ~665万5,556円以下) | 68万円 | ||
| 489万円超~655万円以下 (665万5,556円超 ~850万円以下) | 63万円 | ||
| 655万円超~2,350万円以下 (850万円超 ~2,545万円以下) | 58万円 | ||
残念ながら、住民税の基礎控除(43万円)は据え置きとなります。



低所得者層への税負担軽減を強化しつつ、高所得者には従来どおり制限を設ける仕組みです。基礎控除の改正は会社員だけでなく個人事業主・自営業者も対象になります。
給与所得控除の見直し
給与所得控除は、給与所得者が収入から自動的に差し引ける「必要経費相当額」ですが、その最低保障額が引き上げられます。
• 改正前: 最低55万円
• 改正後: 最低65万円に引き上げ。
この給与所得控除の最低保障額65万円と、基礎控除額(95万円)の合計額を基に、所得税の非課税ラインが従来の103万円から「160万円(95万円+65万円)」へ大幅に引き上げられます。
| 【改正前】 給与収入金額 | 【改正前】 給与所得控除額 | 【改正後】 給与収入金額 | 【改正後】 給与所得控除額 |
|---|---|---|---|
| 162.5万円以下 | 55万円 | 190万円以下 | 65万円 |
| 162.5万円超~180万円以下 | 収入金額 × 40% − 10万円 | ||
| 180万円超~360万円以下 | 収入金額 × 30% + 8万円 | 190万円超~360万円以下 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
| 360万円超~660万円以下 | 収入金額 × 20% + 44万円 | 360万円超~660万円以下 | 収入金額 × 20% + 44万円 |
| 660万円超~850万円以下 | 収入金額 × 10% + 110万円 | 660万円超~850万円以下 | 収入金額 × 10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円 | 850万円超 | 195万円 |
特定親族特別控除の新設
大学生の親御さんにとって最も注目すべき改正が、この 「特定親族特別控除」 です。若年層の就業支援を目的として、新たに特定親族特別控除が創設されます。
• 対象者: 19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人(給与収入で言えば、123万円超188万円以下)。
• 控除額: 特定親族の合計所得金額に応じて、3万円から最大63万円が控除されます。
これにより、大学生のお子さんがアルバイトで 123万円を超えて稼いでも、188万円以下であれば親は段階的に控除を受けられる ようになります。
特に 年収150万円以下(所得85万円以下) であれば、従来の特定扶養控除と同じ 63万円の控除 が適用されます。
特定親族特別控除については、こちらの記事で詳しく解説しておりますので、ご覧ください。
【町田市の税理士が解説】年末調整シリーズ第3回: 令和7年税制改正で新たに追加された特定親族特別控除とは?大学生の子を持つ親御さんに朗報!
配偶者特別控除の範囲拡大
基礎控除の見直しに伴い、配偶者特別控除の対象範囲も広がります。
- 改正前: 所得48万円超〜133万円以下
- 改正後: 所得58万円超〜133万円以下
これにより、配偶者の年収が 103万円から123万円まで 引き上げられても控除対象となります。
さらに、配偶者特別控除の満額(38万円)が適用される年収ラインも 150万円 → 160万円 に拡大されました。
住宅ローン控除・残高証明書不要に
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)については、控除の拡充措置が令和7年についても引き続き適用されます。
さらに実務上の変更として、年末調整において「調書方式」の適用を受ける人は、給与の支払者に提出する「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」に、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の添付が不要となります。これは、金融機関から提供された残高情報を国税庁が直接取得し、納税者本人に提供する仕組みを利用するためです。これにより、従業員・事業主双方の事務負担が軽減されます。
4.年末調整書類への影響
扶養控除等申告書の記載方法(改正後)
• 扶養控除等申告書のB欄に記載される「控除対象扶養親族」という名称が、「源泉控除対象親族」に変更されます。
• 「源泉控除対象親族」には、従来の控除対象扶養親族(所得58万円以下)に加え、特定親族の一部(年齢19歳以上23歳未満で所得58万円超100万円以下)が含まれることになります。
• この源泉控除対象親族の記載は、令和8年以降の毎月の源泉徴収税額の計算に反映されます。
特定親族特別控除の記載欄の新設
新たに創設された 特定親族特別控除 を受けるためには、従業員が 「給与所得者の特定親族特別控除申告書」 を提出する必要があります。
この申告書は、国税庁の予定では、「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」との兼用様式となる予定です。
該当する従業員は、この申告書に以下の情報を記載する必要があります。
1. 特定親族の氏名、個人番号(マイナンバー)、続柄。
2. 特定親族の本年中の合計所得金額の見積額。
3. 上記見積額に基づき計算した特定親族特別控除の額。



せっかく新設された制度ですが、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を記載しない場合、特定親族特別控除 を受けることができないため、注意が必要です!
実務での注意点(収入 vs 所得の判定、青色事業専従者の除外など)
税制上の判定では、「収入」と「所得」の違いを正確に理解しておくことが不可欠です。
| 用語 | 定義 | 令和7年改正後の主な要件 |
|---|---|---|
| 収入 | 実際に受け取った金額 (給与の額面など) | 103万円→123万円 (扶養親族の年収目安) |
| 所得 | 収入から経費や控除 (給与所得控除など)を引いた金額 | 48万円→58万円 (扶養親族の合計所得金額要件) |
特定親族特別控除の判定基準は「合計所得金額」(58万円超123万円以下)であり、給与収入のみの場合の目安は123万円超188万円以下となります。
また、特定親族特別控除の対象となる特定親族には、納税者の配偶者(配偶者控除制度があるため)や青色事業専従者(給与の支払を受ける人)は含まれない点に注意が必要です。
【担当者向け】源泉徴収簿の記載方法
令和7年分の年末調整では、国税庁が提供している従来の源泉徴収簿の様式では特定親族特別控除に対応していません。このため、特定親族特別控除を適用する際は、源泉徴収簿の余白に次のように記載する必要があります。
「特定親族特別控除額〔 XXX,XXX 円〕」
5.よくある質問(FAQ形式)
- 103万円の壁がなくなって160万円まで非課税になったら、社会保険の壁も気にしなくていいですか?
-
いいえ、社会保険の壁は引き続き存在し、税金の壁とは別物です。所得税が非課税となるラインは160万円に引き上げられましたが、社会保険上の扶養から外れるラインは以下のとおりです。
• 106万円の壁: 勤務先の従業員規模や労働時間などの条件を満たす場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務が発生します。
• 130万円の壁: 106万円の壁の条件を満たさなくても、年収130万円以上になると社会保険の扶養から外れ、自身で社会保険料(国民年金・国民健康保険)を支払う必要があります。なお、令和7年10月1日以降、19歳以上23歳未満限定で、130万円の壁が150万円の壁に変わります。
税金と社会保険の両方を考慮し、ご自身のライフプランに合った働き方を選択することが重要です。
- 基礎控除が変わるようですが、自分の控除額はいくらになりますか?
-
基礎控除額は、あなたの「合計所得金額」によって決まります。令和7年・8年分においては、所得金額が132万円以下であれば最大95万円の控除が受けられます。
年末調整では、従業員自身が正確な所得の見積額を算出し、「基礎控除申告書」に記載することが求められます。所得額によって控除額が変わるため、もし所得の見積もりが難しい場合は、給与の支払者や税理士に相談しましょう。
- 大学生のアルバイト収入が125万円の見込みです。特定親族特別控除は受けられますか?
-
はい、特定親族特別控除の要件に該当する可能性が高いです。
特定親族特別控除の対象は、合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(給与収入で123万円超188万円以下)です。給与収入が125万円の場合、給与所得控除(65万円)を引いた所得は60万円(125万円-65万円)となり、適用対象範囲内(58万円超123万円以下)に収まります。この場合、親は63万円の特定親族特別控除を受けることができます。
- 特定親族特別控除の適用を受けるためには、いつまでに手続きが必要ですか?
-
年末調整で控除の適用を受けようとする従業員は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに「特定親族特別控除申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。実務的には、11月頃に、お勤め先から当該書類等の提出期限を設定されますので、定められた提出期限までに、必要書類をお勤め先へご提出ください。
また、特定親族特別控除の要件(親族の合計所得金額など)の判定は、申告書を提出する日の現況によって行われます。可能な限り、正しく見積もりましょう。
6.まとめと実務アドバイス
改正のポイントを再整理
令和7年度税制改正は、税制上の「働き控え」を解消し、子育て世帯を支援するために、基礎控除と給与所得控除を引き上げ、若年層の扶養親族に関する特定親族特別控除を新設したことが核となります。
これにより、所得税の非課税ラインが「103万円の壁」から「160万円の壁」へと大きく変わりましたが、社会保険の壁(106万円・130万円(NEW150万円))は依然として存在するため、税制と社会保険を切り分けて考える必要があります。
親としての対応方針(アルバイトと学業のバランス)
大学生のお子さん(12月31日時点で19歳以上22歳以下の親族)を持つ親御さんにとって、今回の特定親族特別控除の創設は朗報です。
お子さんの年収が103万円を超えても、188万円以下であれば親の税負担が急激に増えることはなくなりました。そのため、従来のように、税金を気にしてアルバイトを抑制する必要性は薄れましたが、大学生の本業はあくまでも勉学であるため、親としては、お子さんが学業と両立できる範囲で働くことをサポートする必要はあります。
なお、社会保険上の扶養から外れる場合には、お子さんの手取りが一気に減ることになります。令和7年10月1日以降、19歳以上23歳未満の場合、社会保険の壁が、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。詳しくは、こちらをご覧ください。
税理士としての視点からの注意喚起
【給与所得者・親御さんへ】
新しい控除の適用は自動ではありません。特定親族特別控除の適用を受けるためには、忘れずに「特定親族特別控除申告書」を勤務先に提出する必要があります。申告漏れがないよう、勤務先からの案内を注意深く確認してください。また、新しくなった年収の壁を正しく理解し、働き方について、お子さんとすり合わせをしておきましょう。
【事業主・人事労務担当者へ】
今回の改正は制度が複雑化しており、年末調整実務において混乱が予想されます。特に以下の点に注意が必要です。
1. 従業員への周知徹底: 基礎控除の変動や新設された特定親族特別控除について、対象となる従業員(特に19〜23歳の扶養親族を持つ人)に早めに正確な情報を伝え、申告漏れを防ぐことが最重要課題です。
2. 申告書様式の確認と実務対応: 令和7年分の年末調整では、改正後の基礎控除や給与所得控除を反映した新しい「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用し、計算を行う必要があります。また、源泉徴収簿の様式対応など、実務上の細かい変更点も多いため、国税庁の最新情報や改正後の税額表(令和7年12月精算用)を必ず確認してください。



令和7年度改正は、「働き控えの解消」と「子育て世帯支援」を同時に進める大きな一歩です。
ただし、税制と社会保険の両面を正しく理解しなければ、思わぬ負担増につながる可能性もあります。複雑な制度変更を共に乗り越え、正確な年末調整を行いましょう!
相談できる税理士がいない場合には、お気軽にこちらまでお問い合わせください。

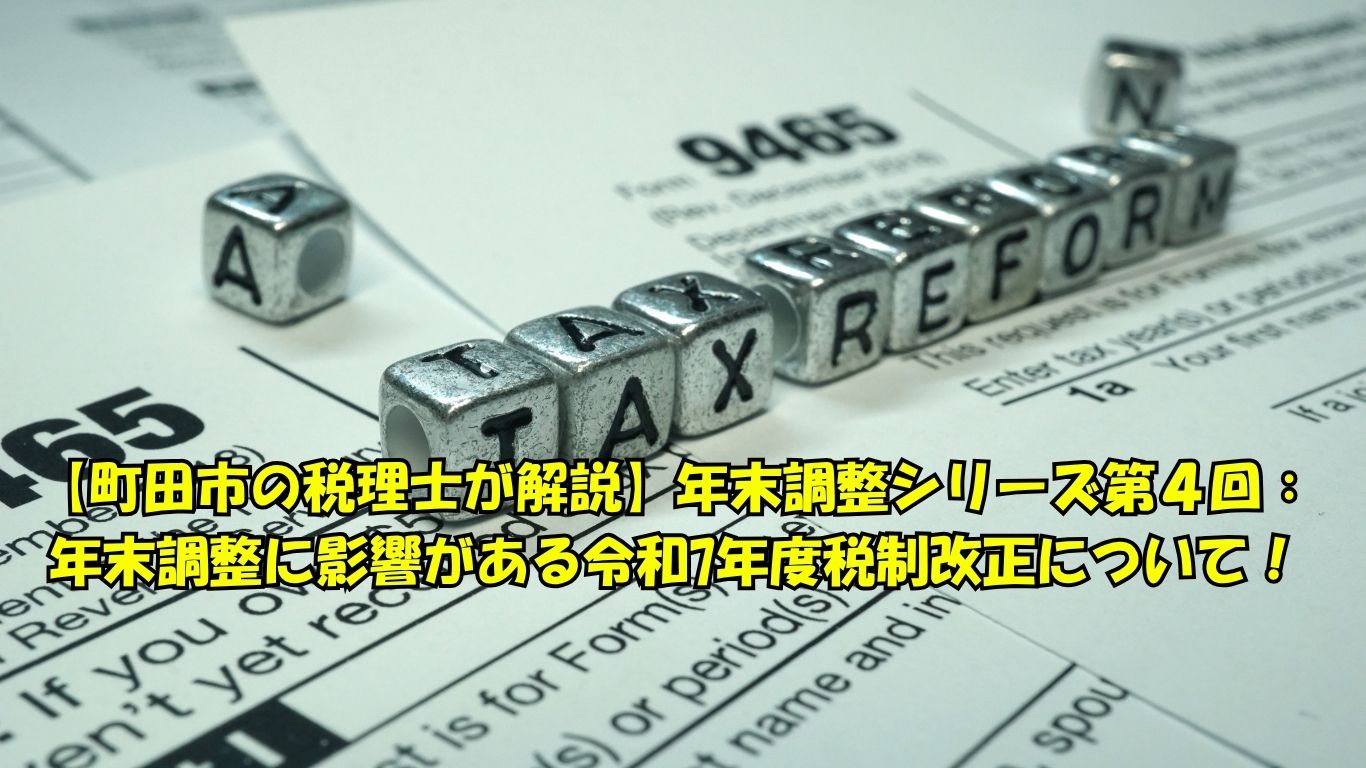


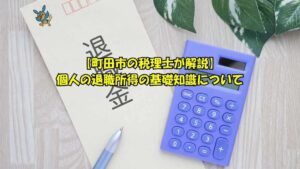


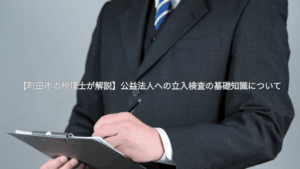

コメント