 ミミレイドン
ミミレイドンおはようございます、ボス!昨日まで6回分の銀行融資シリーズお疲れ様でした。事業を行う上で、資金繰りはとても大切だと心得ておりますので、大変参考になりました。



資金繰りと言えば、最初に入った税理士法人で、お客様から「納税資金がない」と相談があったことがあります。



それは大変ですね。昨日までの銀行融資シリーズが役に立ちますね。



借入ができない事態も想定されますので、そもそも、どの月にどの税金がどのくらい発生するのかをある程度把握しておく必要はあると思います。ということで、今朝は、個人事業主・フリーランスの年間の納税スケジュールについて、解説していきます。
1.はじめに:個人事業主・フリーランスの納税スケジュール
納税スケジュールの管理の必要性
会社員時代とは異なり、個人事業主にとって納税スケジュールの管理は事業の命綱です。この管理を怠ると、せっかく黒字を出していても、急な税金ラッシュで資金がショートする「黒字倒産」の危険性さえあります。事業の資金繰りだけを想定していると、急な税金に対応できないことがありますので、予め税金の納税スケジュールは把握しておく必要があります。
納税期限に送れるリスク
「知らなかった」「うっかり忘れた」「何か納付書は届いたが詐欺かと思ってた」では済まされません。納税期限に遅れると、原則として延滞税や無申告加算税などといったペナルティ(付帯税)が自動的に課されてしまいます。侮っていると、とんでもない金額になることもあります。無駄な支払いを避けるためにも、年間の納税スケジュールは頭に入れておきましょう。
2.年間申告・納税スケジュール表
個人事業主が1年を通じて納める主要な税金や社会保険料の期限を、一覧表にまとめました。
なお、地方税(住民税、固定資産税、償却資産税、事業税など)は自治体によって納期限が異なる場合があるため、必ずご自身の自治体からの通知書をご確認ください。下記のスケジュール表では、参考として、町田市の納税スケジュールを示しております。
| 納付月 | 納付対象(税目) | 納付期限 | 納税先 | ポイント |
| 3月 | 所得税(確定) | 3月15日 (申告・納付期限) | 国 (税務署) | 確定申告と同時納付。 |
| 消費税(確定) | 3月31日 (申告・納付期限) | 国・地方 | 課税事業者のみ。 | |
| 4月 | 所得税(確定) 振替納付 | 4月20日頃 | 国 (税務署) | 振替納税を利用した場合。 |
| 消費税(確定) 振替納付 | 4月30日頃 | 国・地方 | 振替納税を利用した場合。 | |
| 5月 | 自動車税/軽自動車税 | 5月末 (原則一括) | 地方 (都道府県/市町村) | 資産を持つ者、車両所有者。 |
| 6月 | 個人住民税 (第1期) | 6月末 | 地方 (市区町村等) | 賦課課税方式で通知が届く。 |
| 固定資産税・償却資産税(第1期) | 6月末 | 地方 (市町村等) | 自治体により期限が異なる。 | |
| 国民健康保険料 (第1期) | 6月頃から開始 | 地方 (市区町村等) | 6月~翌年3月の10回払いが一般的。 | |
| 7月 | 源泉所得税 (納期特例) | 7月10日 (1月~6月分) | 国 (税務署) | 従業員等に給与/報酬を支払う場合。 |
| 所得税 予定納税(第1期) | 7月31日 | 国 (税務署) | 前年所得税額15万円超の場合。 | |
| 8月 | 個人事業税 (第1期) | 8月末 | 地方 (都道府県) | 課税対象業種かつ所得290万円超の場合。 |
| 個人住民税 (第2期) | 8月末 | 地方 (市区町村等) | ||
| 消費税 中間申告/納付 | 8月末 (年1回の場合) | 国・地方 | 前年消費税額が48万円超の場合。 | |
| 9月 | 固定資産税・償却資産税(第2期) | 9月末 | 地方 (市町村等) | |
| 10月 | 個人住民税 (第3期) | 10月末 | 地方 (市区町村等) | |
| 11月 | 所得税 予定納税(第2期) | 11月30日 | 国 (税務署) | 前年所得税額15万円超の場合。 |
| 個人事業税 (第2期) | 11月末 | 地方 (都道府県) | ||
| 12月 | 固定資産税・償却資産税(第3期) | 12月末 | 地方 (市町村等) | 町田市の固定資産税は12/25 |
| 翌1月 | 源泉所得税 (納期特例) | 1月20日 (7月~12月分) | 国 (税務署) | |
| 償却資産税申告期限 | 1月31日 | 地方 (市町村等) | 申告期限であることに注意。 | |
| 個人住民税 (第4期) | 1月末 | 地方 (市区町村等) | ||
| 固定資産税 (第4期) | 1月末 | 地方 (市町村等) | ||
| 翌2月 | 償却資産税 (第4期) | 2月末 | 地方 (市町村等) |
3.各税目について
多くの個人事業主が直面する税金について、納付のタイミングと仕組みを詳しく見ていきましょう。
所得税(確定)
所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得(儲け)に対して課税される国税です。
- 申告・納付期限: 原則として、翌年の3月15日までです。
- 納付方法: 納税者が自ら税額を計算して納める申告納税方式をとります。
- 注意点: 納付書などは税務署から送られてこないため、期限までに自分で納付手続きを完了させる必要があります。
所得税(予定)
予定納税は、所得税の一部をあらかじめ前払いする制度です。
- 対象者: その年の5月15日現在で確定している前年分の所得税および復興特別所得税の金額(予定納税基準額)が15万円以上となる方です。
- 納付時期: 基準額の3分の1の金額を、第1期と第2期に分けて納付します。
第1期分: その年の7月1日~7月31日まで。
第2期分: その年の11月1日~11月30日まで。 - 仕組み: 予定納税額は、翌年の確定申告の際に、確定税額から差し引かれ精算されます(税金の前払いのため)。税務署長から、その年の6月15日までに書面またはe-Taxで通知が来ますので、自分で計算する必要はありません。
消費税(確定)
消費税は、国内で商品やサービスを提供した際に課税される間接税です。
- 対象者: 課税期間の基準期間(個人事業主は前々年)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、原則として納税義務が発生します。また、適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)は、基準期間の売上高にかかわらず納税義務が免除されません。
- 申告・納付期限: 原則として、その年の翌年3月31日までです。
- 注意点: 消費税の確定申告の期限と納付期限は同じです。また、納付書等の送付はないため、所得税と同様に自分で期限を管理する必要があります。
消費税(予定)
消費税も、前払いの中間申告・納付があります。
- 対象者: 前年分の消費税額(地方消費税額を除く)が、48万円を超える課税事業者が対象となります。
- 納付時期: 納付回数は前年分の確定消費税額によって異なりますが、前年分の消費税額が48万円超400万円以下の多くの事業者は、8月末に1回予定納税をすることが一般的です。
住民税
住民税は、都道府県と市区町村に納める地方税です。所得税と同じく個人の所得(儲け)に対してかかりますが、納付の仕組みが大きく異なります。
- 課税の仕組み: 前年1月1日~12月31日までの所得に基づき、自治体が税額を計算し通知する賦課課税方式です。確定申告のデータが自治体と共有されるため、原則として所得税の確定申告をしていれば、住民税の申告は不要です。
- 納付時期: 毎年5月下旬~6月上旬頃に通知書が届き、個人事業主は普通徴収として、通常年4回に分けて納付します。
第1期:6月末
第2期:8月末
第3期:10月末
第4期:翌年1月末
個人事業税
個人事業税は、事業を営む個人に課される地方税です。
- 対象者: 全員に課されるわけではありません。課税対象となる一定の業種に該当する事業を行っている方が対象です。
- 課税基準: 事業所得が290万円を超えると課税されます。
- 納付時期: 住民税と同様に賦課課税方式で通知が届き、通常8月末と11月末の2回に分けて納付します(納税額が少ないと8月の1回にまとめられることもあります。)。
源泉所得税
源泉所得税は、事業主が、従業員や外部のフリーランス(一部の報酬)に対して金銭を支払う際に、あらかじめ差し引いて国に納める税金です。
- 納付時期
原則: 給与や報酬を支払った月の翌月10日までとなります(従業員を雇用している場合には、基本毎月支払いが発生します。)。
納期特例: 給与を支払う者が従業員10人未満の場合、源泉所得税を半年分まとめて納める特例を利用できます。
1月~6月分:7月10日。
7月~12月分:翌年1月20日。
固定資産税
固定資産税は、土地や家屋、事業用の償却資産(これらを固定資産といいます)を持っていることに対して、市町村から課される税金です。
- 納付時期: 原則として年4回に分けて納付します(4月、7月、12月、2月など)。上記表は町田市の納税スケジュールとなりますので、必ずご自身の市区町村の納付期限をご確認ください。
- 注意点: 納付期限は自治体によって異なるため、届いた納付書で確認が必要です。事業に使用している固定資産にかかる固定資産税は必要経費にできます。
償却資産税
償却資産税は、固定資産税の一部であり、事業のために使用している償却資産(パソコン、機械装置、工具、器具備品など)に対して課税されます。おおむね固定資産税の納税時期と同様になりますが、上記表は町田市の納税スケジュールとなりますので、必ずご自身の市区町村の納付期限をご確認ください。
- 手続き: 納税自体は固定資産税と一緒ですが、毎年1月31日(または翌平日)までに、所有する償却資産の状況を自治体へ申告する必要があります。
国民健康保険料・国民年金
これらは税金ではありませんが、個人事業主が必ず支払う必要があり、資金繰り上、税金と同じくらい重要な支出です。
- 国民健康保険料(国保): 前年の所得と被保険者の人数をベースに算定され、通常6月頃に通知があり、6月〜翌年3月の10回に分けて支払うのが一般的です。確定申告のデータに基づいて計算されるため、所得が大幅に上がると国保料も大幅に上がります。
- 国民年金保険料: 日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、保険料は毎月支払うこととなります(原則一律)。2025年度現在は、17,510円/月です。昨年度より530円増加しました。
4.実務的アドバイス
納税スケジュールを把握しただけでは不十分です。資金繰りの失敗で事業を停滞させないために、実際に私がお客様にお伝えしている3つの対策を伝授します。
(1).e-Taxや口座振替を活用して納付忘れを防止
多忙な個人事業主は、支払い忘れを防ぐ仕組み作りが必須です。
①. 所得税/消費税は「振替納税」を最大限活用する
確定申告で納付する所得税(国税)の納税方法で最もおすすめなのは振替納税(口座振替)です。
振替納税は、通常の納付期限(3月15日)よりも約1か月後、例年4月中旬頃に口座から引き落とされます。この「後払い」になることで、確定申告直後の資金繰りに余裕が生まれます。
一度手続きをすれば、翌年以降も自動的に引き落とされますが、事前に「預貯金口座振替依頼書」を税務署に提出する必要があります。
②. クレジットカード納付やe-Taxのダイレクト納付も検討する
所得税の納付は、e-Taxによるダイレクト納付(口座からの直接納付)や、クレジットカード納付も可能です。
特にクレジットカード納付は、決済手数料がかかりますが、実際の引き落とし日はカード会社の設定日になるため、実質的な後払いとなり資金繰りに役立ちます。
③. 地方税(住民税、国保)は口座振替を申し込む
住民税や国民健康保険料など地方税も、多くの自治体で口座振替に対応しています。普通徴収(年4回など)の場合、納付書を毎回管理する必要がなくなり、納め忘れのリスクを大幅に軽減できます。口座振替の申込期限は、第1期に間に合わせるためには4月下旬~5月上旬頃に設定されていることが多いので、自治体の情報を確認しましょう。
(2).資金繰りを見据えて「納税用口座」を分けて管理する
納税対策とは、「要するにお金を残しておくこと以外にはない」のです。
売上金が入ってきたら、その中から将来発生する税金分をすぐに分離して、絶対に手を付けない「納税用口座」へ移す仕組みを作りましょう。
この「納税貯金」をしておくことで、急な税金ラッシュ(特に5月~8月の上期は支払いが集中しがちです)で慌てることがなくなり、精神的負担も大きく軽減されます。あなたの売上から常に何パーセントかを納税貯金として避けておく計画(例えば、消費税や所得税の目安額)を立てることが非常に重要です。
(3).国保や住民税は「前年所得ベース」で決まることを意識する
多くの個人事業主が驚き、資金ショートの原因となるのが、住民税や国民健康保険料(国保)の計算方法です。これらの税金・保険料は、「昨年の所得(確定申告の数字)で計算され、今年支払う」タイムラグがあります。
- 前年が好調だった場合: 確定申告の所得金額が大幅に上がると、翌年の住民税や国保料、事業税の負担も大幅に増加します。
- 今年業績が下降した場合: 高収入だった前年ベースで計算された税金を、収入が減少した今年のキャッシュフローから払うことになり、負担感が非常に大きくなります。
特に事業が急成長した翌年や、所得が大きく変動する可能性がある場合は、このタイムラグを意識し、より多くの納税貯金を確保しておく必要があります。
5.まとめ
個人事業主の納税は、会社員のように給与天引きで自動的に完了するものではありません。納税者が自らスケジュールを把握し、資金を計画的に確保する経営者としての責任が伴います。資金ショートしないための対策について、まとめると、
- 年間カレンダーの確認と「見える化」: 確定申告後の6月~11月にかけて、住民税、国保、事業税、予定納税といった税金ラッシュが待っています。カレンダーをデスク周りなどに貼り、納付すべき時期を常に意識しましょう。
- 納税資金の確保: 売上を全額使わず、将来の納税のために納税用口座に積み立てておく仕組みを徹底してください。
- タイムラグの意識: 住民税や国保料は「前年所得」で決まるため、今年の資金繰りに大きな影響を与えることを忘れないでください。
納税計画をしっかりと立てることは、あなたの事業を安定させ、さらなる成長を可能にする土台となります。複雑な税金計算や申告の手間を軽減するためには、税理士に依頼することも有効です。



資金ショートの不安から解放され、本業に集中できる環境を整えていきましょう!相談できる税理士がいない場合には、お気軽にこちらまでお問い合わせください。

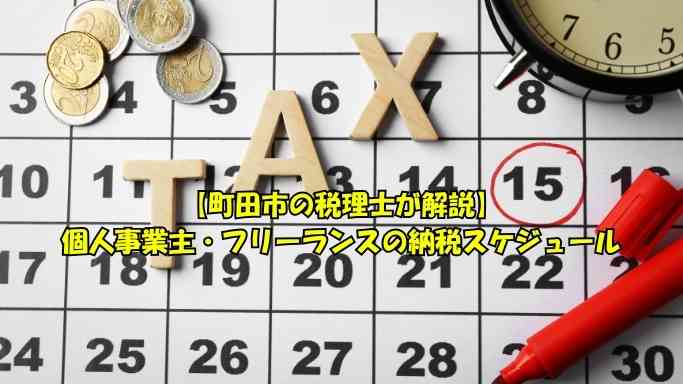








コメント