 ミミレイドン
ミミレイドンボス、おはようございます!10月ラストの週ですね!今朝のテーマはなんでしょうか?



今朝は、お問い合わせのあった一般財団法人の解散と清算の手続きについて、解説していきます。



結構マニアックなテーマですね!



確かに、「一般財団法人の解散と清算」は、非常に専門的なテーマになります。今回は、一般的な需要ではなく、お問い合わせいただいたお客様にわかりやすくご説明できるように、私の頭の整理のためにこのテーマを選びました。
法人の「終わり」の手続きは、往々にして「始まり」よりも複雑です。しかし、この記事を読めば、その複雑な道のりも明確なステップに分かれ、スムーズに進めるための道筋が見えるはずです。正確な知識を持ち、ミスなく手続きを完了させましょう!
1.はじめに
(1).一般財団法人とは何か
一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体です。その主な目的は、非営利な活動にあります。一般財団法人は、剰余金や残余財産の分配を目的としないという点で、営利を目的とする株式会社とは異なります。
この法人は、設立者が定めた目的の実現のために設立される、という特性を持っています。
(2).なぜ解散・清算が必要になるのか
一般財団法人の解散とは、法人の事業活動を終了させ、法人格を消滅させる手続きの第一歩です。解散によって営業活動を停止し、その後、資産や負債を整理し、最終的に法人を法律上消滅させる清算手続きへと移行します。
解散・清算が必要となる主な理由は、設立の目的を果たした場合や、事業の継続が事実上不可能となった場合などが挙げられます。
2.解散の主な事由(法人法第202条)
一般財団法人が解散する事由は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法人法)第202条に定められています。
特に重要な点として、一般財団法人は、設立者の定めた目的実現のために存在する性質上、評議員会やその他の機関による決議によって自主的に解散することは原則として認められていません。
(1).定款で定めた存続期間の満了
定款において、あらかじめ法人の存続期間を定めていた場合、その期間が満了したときに解散します。これは登記事項です。



一般財団法人は評議員会の決議によって自主的に解散することは原則認められていません。自主的に解散したい場合の裏ワザ的な手続き方法として、評議員会の決議によって、存続期間の定めに関する定款を変更(追加)するなどの方法が考えられます。『定款例:定款第○条 当法人の存続期間は、令和○年○月○日までとし、その満了をもって解散する。』
なお、存続期間の定めは、定款の相対的記載事項となるため、定めた場合は登記事項となり、登記が必要となります。登録免許税は3万円です。
(2).定款で定めた解散の事由の発生
定款に、特定の事業目的が達成された場合など、解散の事由を定めていた場合に、その事由が発生すると解散します。これも登記事項です。
(3).事業の成功が不能となった場合
基本財産の滅失や、その他の事由により、一般財団法人の目的である事業の成功が不能となった場合も解散事由です。 ここでいう「事業の成功の不能」とは、その目的が法律上または事実上達成不可能であることが確定した状態を指します。
(4).合併(消滅法人になる場合)
他の一般社団法人や一般財団法人と合併し、当該法人が消滅法人になる場合に解散します。この場合、清算手続きを行う必要はありません。
(5).破産手続開始の決定
法人が破産手続開始の決定を受けた場合も解散します。
(6).裁判所による解散命令
解散を命ずる裁判や、解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったときも解散事由です。例えば、法人の設立が不法な目的に基づいていた場合や、業務執行理事が法令・定款を逸脱・濫用する行為を継続的に行った場合などには、法務大臣などから解散命令の措置がとられることがあります。
(7).純資産額が2期連続で300万円未満となった場合
これは一般財団法人特有の非常に重要な解散事由です。
ある事業年度と、その翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額が、いずれも300万円未満となった場合には、その翌事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散します。
これは、一般財団法人が設立時だけでなく、存続中においても一定規模の財産保持義務を課されているためです。



もし、一般財団法人が最後に登記をしてから5年間、理事変更などの登記を一切行っていない場合、休眠法人と見なされ、法務局が職権で解散登記を行うことがあります(みなし解散)。
法務局はまず、事業を廃止していない旨の届出をすべきことを官報で公告し、その公告から2か月以内に届出がない場合、解散したものとみなされます。みなし解散の登記がされた後でも、3年以内であれば評議員会の特別決議によって継続の登記を行うことで、法人を復活させることができます。継続の意思がある場合は、できるだけ早期に「法人継続の登記」を行い、その登記事項証明書を税務署に提出する必要があります。
3.解散手続きの流れ
解散事由が発生すると、法人は清算法人となり、事業活動から清算事務へと目的が変わります。
(1).解散事由の確認と発生
解散事由が発生した日(定款の期間満了日や純資産要件を満たした定時評議員会終結時など)を特定します。
(2).清算人の選任
解散後は、法人の財産を整理する清算人を置かなければなりません。清算人とは、現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しを行う担当者です。
清算人の選任方法は以下の通りです。
- 定款で定める者。
- 評議員会の決議によって選任された者。
- 上記1, 2の定めがない場合、解散のときにおける理事が清算人となります(法定清算人)。
清算人の数は、清算人会を置かない場合は1人以上で構いませんが、清算人会を置く場合は3人以上が必要です。
(3).解散登記と清算人登記(法務局)
解散事由が発生した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に解散登記と清算人の就任登記を申請しなければなりません。
この登記を行うことで、法人が清算手続きに入ったことを広く知らせることができます。解散の登記がされると、解散前の理事会、理事、代表理事に関する登記は職権で抹消されます。



一般財団法人が解散登記された時点で、理事会は消滅してしまうのですね。評議員会の招集とかはどうするのでしょうか?



はい、法人の業務執行機関である理事会が、法人の通常業務を行う必要がなくなるため、この時点で消滅となります。以降は「清算人」が業務執行を担います。したがって、評議員会の招集も清算人が選任されている場合は、清算人が評議員会を招集する権限を持ちます。なお、定款に清算人の定めがなく、評議員会で清算人を選任しない場合、解散時の理事がそのまま清算人となるため、その理事(清算人)が招集権限を持ちます。
4.清算手続きの流れ
清算手続き(清算事務)とは、法人の財産を整理し、債務を弁済し、残った財産を処理して法人格を消滅させるまでの過程です。
(1).財産目録・貸借対照表の作成
清算人は、就任後遅滞なく、解散が生じた日における法人の財産の現況を調査し、財産目録および貸借対照表(BS)を作成する必要があります。
これらの書類は、清算法人の財産状況を評議員に開示し、残余財産額を予測するための情報を提供するために、評議員会に提出し承認を受けなければなりません。
(2).債権者保護手続き
清算人は、債権者を保護するため、以下の手続きを実施しなければなりません。
- 官報公告の実施: 債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告します。
- 期間: この債権申出期間は2か月を下ることができません。
- 各別の催告: 知れている債権者には、個別にこれを催告(通知)しなければなりません。
この債権申出期間(最低2か月)内は、原則として債務の弁済をすることはできません。期間内に債権を申し出なかった債権者は、清算から除斥される旨を付記する必要があります。
(3).現務の結了・債権債務の整理
清算人は、解散した法人の現務の結了、債権の取立て、および債務の弁済を行います。
- 現務の結了
解散前に着手していた事務を完了させることを指し、例えば、従業員との雇用契約の解消や事務所の賃貸借契約の解約などが該当します。 - 債権の取立て
売掛金などの債権について履行を受けたり、不動産や有価証券などを売却し財産を換価(現金化)します。 - 債務の弁済
買掛金などの債務を債権者に対して弁済します。
(4).残余財産の処理
債務をすべて弁済し、なお法人に財産が残った場合、これを残余財産といいます。
- 原則: 残余財産の帰属先は、定款の定めに従います。
- 評議員会の決議: 定款に定めがない場合、清算法人の評議員会の決議によって帰属先を定めます。
- 国庫帰属: 上記のいずれによっても帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属します。
参照:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第239条



注意点として、一般財団法人は、株式会社とは異なり、定款によって設立者に残余財産の分配を受ける権利を与える旨を定めることはできません。ただし、定款の定めがない場合、解散後の評議員会の決議によって設立者を帰属先とすることは可能です。
5.清算結了と登記
清算事務が完了し、法人の財産が皆無になった時点で、法人格を消滅させる最終段階に入ります。
(1).決算報告書の作成と評議員会での承認
清算人は、清算事務が終了したときは、清算事務に関する決算報告書を作成し、評議員会の承認を受けなければなりません。この決算報告の承認をもって、清算は結了することになります。
(2).清算結了登記(承認日から2週間以内)
評議員会で決算報告の承認を受けた後、その承認の日から2週間以内に、法務局へ清算結了の登記を申請します。
清算結了登記に必要な登録免許税は、2,000円です。
(3).登記簿の閉鎖
清算結了の登記がされると、一般財団法人の法人登記簿は閉鎖され、法律上、法人格が消滅します。
なお、会社の印鑑証明書は、清算結了の登記がされた後では取得できなくなります。
6.税務・行政への届出
税理士の視点から特に強調したいのは、解散・清算手続きにおける税務処理は非常に厳格な期限が設けられているということです。手続きが完了したら、速やかに各行政機関へ届出を行う必要があります。
(1).税務署・都道府県税事務所・市区町村への異動届
解散登記後、清算結了登記後には、以下の行政機関に異動届出書を提出し、法人の状況が変更したことを通知する必要があります。
- 税務署(国税)
- 都道府県税事務所(地方税)
- 市区町村(地方税)
異動届出書には、解散後の登記事項証明書(解散時)、または閉鎖事項全部証明書(清算結了時)を添付します。提出期限は特に設けられていませんが、解散・清算結了登記完了後、速やかに行う必要があります。
【超重要】解散・清算に伴う法人税等の申告期限
解散に伴い、事業年度の区切りが変わるため、確定申告の期限に特に注意が必要です。
| 申告の種類 | 対象期間 | 期限 |
| 解散確定申告 | 事業年度開始の日から解散日まで | 解散日の翌日から2か月以内(原則) |
| 清算中の各事業年度 | 解散日の翌日から1年ごとの期間 | 各事業年度終了日の翌日から2か月以内(原則) |
| 残余財産確定事業年度 | 残余財産確定の日の属する事業年度 | 事業年度終了日の翌日から1か月以内 |
※地方税(住民税、事業税)についても同様に申告が必要です。また、消費税の課税事業者である場合は、法人税の事業年度と同様に、解散の日までを1課税期間として確定申告が必要です。
(2).帳簿の保存義務(7年間)
清算が結了した後も、清算人は、清算結了の登記の日から10年間(ただし、一般財団法人及び一般財団法人に関する法律では10年間ですが、法人税法上の帳簿書類は7年間の保存義務があります)、一般財団法人の帳簿と重要な資料を保存しなければなりません。



清算結了後の帳簿・書類の保存年限は、会社法領域(一般社団・財団法)と税法領域で要件が異なります。複数の法律が異なる保存期間を定めている場合、より長い期間(=10年)を適用するのが安全です。これは、会社法違反や税務調査時の証拠不足を防ぐためです。
7.まとめと注意点
一般財団法人の解散・清算手続きは、解散事由の確認から始まり、登記、債権者保護、財産整理、税務申告、そして清算結了登記という多岐にわたるステップを踏みます。この手続きは最低でも2か月以上かかり、一般的には半年ほどかかることが多いです。
【特に注意すべき重要ポイント】
• 評議員会での自主的解散は不可: 一般財団法人は、一般社団法人のように社員総会決議によって自主的に解散することは原則できません。解散を希望する場合は、定款に存続期間の定めを設ける定款変更決議を行い、存続期間満了による解散を検討する必要があります。
• 純資産300万円未満の解散: 2期連続で純資産額が300万円未満となった場合、翌年度の定時評議員会終結時に解散してしまうため、継続を希望する場合は速やかに資金を拠出し、継続登記を行う必要があります。
• 債権者保護手続きの厳守: 官報公告(2か月以上の期間)と知れたる債権者への個別催告は法律上の義務であり、これを怠ると清算手続きをやり直さなければならないリスクがあります。
• 税務申告の期限厳守: 解散事業年度や残余財産確定事業年度の確定申告には短い期限が設けられています。特に残余財産確定事業年度の確定申告は、期限延長の特例が適用されないため注意が必要です。



解散・清算手続きは、登記や税務の専門知識が不可欠であり、手続きをスムーズかつ法的に間違いなく進めるためには、司法書士や税理士などの専門家へ相談するのが最も確実です。
複雑な法人整理を乗り越え、次のステップへ進むための準備として、ぜひこの記事を役立ててください。
相談できる税理士がいない場合には、お気軽にこちらまでお問い合わせください。



今週も1週間頑張りましょう!

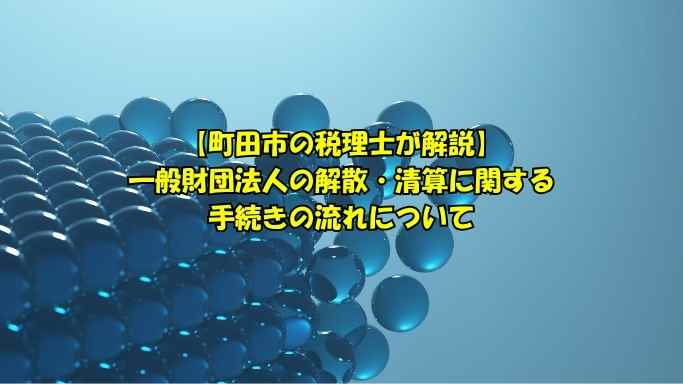








コメント