 ミミレイドン
ミミレイドンボス、おはようございます!早速ですが、昨日アウトラインだけ示してくれた、銀行融資を成功させるためのポイントについて、1つ目の項目の解説よろしくお願いいたします!



わかりました。本日は、融資審査の3大原則について、解説いたします。融資対策として、まずは、融資審査における金融機関の基本的な判断基準を理解するところから始めましょう!



昨日の銀行融資を成功させるためのポイントのアウトラインを確認されたい場合には、次の記事をご覧ください。
【町田市の税理士が解説】<中小企業・個人事業主向け>銀行融資を成功させるためのポイントについて Day0
融資審査における金融機関の基本的な判断基準を理解すること
金融機関(銀行、信用金庫、日本政策金融公庫など)が融資の可否を判断する際の根底にある問いは、ただ一つです。
「貸したお金は、利息を含めて確実に返済されるのか?」
この問いに答えるために、審査担当者は単に過去の決算書(成績表)を見るだけでなく、将来の事業計画と経営者の人間性を総合的に評価します。
特に創業融資の代表格である日本政策金融公庫は、民間銀行が「過去の実績」を重視するのに対し、「将来の可能性=事業計画」を評価して融資を判断する数少ない存在です。
この判断において、金融機関が主に重視する3つの視点、すなわち「信頼の3大原則」を深掘りしていきましょう。
| 融資審査の3大原則 | 審査官の問い(核心) | 対策の鍵 |
|---|---|---|
| 1. 資金の使い道の妥当性 | なぜお金が必要か? その使い方は本当に事業の成長に結びつくのか? | 資金使途の明確化と裏付け資料 |
| 2. 確実な返済能力 | どのように返済していくのか? 利益ではなく、手元の現金(キャッシュフロー)は足りるのか? | 現実的な収支計画と財務指標の改善 |
| 3. 経営者自身の評価 | 計画を実現できる人物か? 熱意と危機管理能力、誠実さはどうか? | 面談での一貫性と準備 (人間性の証明) |
1. 資金の使い道の妥当性(なぜお金が必要か)
融資を申し込む際、借りたお金を何に、いくら使うのか(資金使途)を明確に説明することは、金融機関への信頼を築くための第一歩です。
審査担当者は、提出された書類と経営者の説明から、資金使途が事業計画に対して適正であるか、そして金額に整合性が取れているかを判断します。曖昧な目的(例:「事業資金」「将来のための資金」)は、原則としてマイナス評価につながります。
資金使途は大きく分けて「設備資金」と「運転資金」の2種類で構成されます。それぞれの具体的な対策(使途別の説得力ある説明方法)については、次のA及びBをご覧ください。
A. 設備資金(長期間使用する資産)の妥当性
設備資金とは、店舗の内装工事、機械、車両、PCなどの長期にわたって使用する資産の購入資金を指します。
1. 目的の明確化(Why)
どんな設備を買うのかだけではなく、「なぜその設備投資が必要なのか」という事業上の目的を明確に説明します。例えば、「人手不足解消のための省力化投資のため」や、「新製品製造のための生産能力拡大投資のため」などと具体的に説明する必要があります。
2. 具体的な効果の明示(Effect)
その設備を導入することで、売上や利益にどのようなプラスの影響があるかを数字で示します。例えば、「最新オーブン導入により、生産性が30%向上し、月間人件費を5万円削減できる見込み」や、「客席増設により、座席数を1.5倍にし、月間売上100万円の増加を見込む」などと具体的な効果を明示するようにしましょう。
3. 裏付け資料の添付(How much)
設備資金の金額の根拠として、必ず業者からの見積書を添付し、金額の妥当性を証明します。複数の業者から相見積もりを取っておくと、計画の信頼性が高まります。相場等は必ず確認するようにしましょう。
4. 返済期間の整合性
設備資金の返済期間は、原則として対象設備の耐用年数以内に収める必要があります。長期間使用できる設備への投資は、長期の融資を組みやすくなります。
B. 運転資金(日々の事業運営に必要な費用)の妥当性
運転資金は、仕入れ、人件費、家賃、広告宣伝費など、事業を日々回していくための経常的な費用です。特に重要なのは、「なぜこのタイミングで追加資金が必要なのか」を論理的に説明することです。
1. 「増加運転資金」の論理
単に「運転資金が足りない」という説明では不足です。最も説得力があるのは、売上増加に伴って一時的に資金が不足するケース(増加運転資金)です。例えば、大手取引先との新規契約により売上が増えるが、仕入れや外注費の支払いが先行し、売上金の回収が数ヶ月後になるため等と、具体的に資金が不足する説明することが重要となります。
2. 金額の算出根拠
必要な金額を「売上債権+棚卸資産-仕入債務」などの計算式に基づき、論理的に算出し提示します。例えば、「月間増加売上500万円、原価率60%の場合、先行して必要な資金は500万円×60%=300万円」等と、概算でも具体的な算出根拠を示すことで、信頼感は高まります。
絶対NGな資金使途
- 曖昧な目的(何に使うか特定できない)
- 旧債の返済(別の借入金の返済に充てること。借換目的を除く)
- 投機的な資金(株式投資、FX、事業外の不動産投資など)
- 税金の滞納や借入金等の延滞がある状態。



「借りれるだけ借りたい」や「いくらまでなら借りれますか?」といった発言はやめましょう!
2. 確実な返済能力(どのように返済していくのか)
融資審査において、返済能力は最も重視される要素であると言っても過言ではありません。返済能力の判断は、事業計画書の収支計画(数値計画)を通じて行われます。
金融機関は「利益」だけでなく、「キャッシュフロー(現金の流れ)」を最重要視します。なぜなら、利益が出ていても、売掛金の回収遅延や多額の設備投資があれば、手元の現金が不足し返済が滞る可能性があるからです。
具体的な対策としては、数値計画の現実性と客観的な指標を用いて説明します。
A. 根拠ある収支計画の作成
希望的観測や楽観的すぎる計画は、審査で「非現実的」「甘い」と判断され、信頼を失いますので注意が必要です。
1. 売上予測のロジック
売上予測は、例えば「客数×単価×営業日数」といったその業種に応じた具体的な計算式で根拠を明示しましょう。
良い例: 平日営業のカフェで「1日平均50名来店 × 客単価750円 × 月22営業日 = 月商約82.5万円」。
悪い例: 「市場が伸びているから儲かるはず」や、「開業初月から100万円売上」のように、根拠がない予測は信頼を失います。
2. 資金繰り表の活用
月ごとの現金収入・支出の流れを予測し、現金残高の推移を明示する「資金繰り表」は必須です。これにより、資金がショートするリスクがないことを証明します。「資金繰り表」を作っているというだけでも信頼感は高まります。
3. リスクと対策の明示
想定されるリスク(競合の激化、市場縮小、売上が計画通りにいかなかった場合)を正直に記載し、それに対する具体的な対応策(例えば、赤字でも3ヶ月回せる運転資金の準備、コストカット、販路の見直しなど)を示すことで、経営者の危機管理能力をアピールできます。
B. 銀行が用いる「返済能力を測る3つの重要指標」
銀行は、企業の財務状況を評価する際、「格付け」を行い、その中で以下の3つの指標を特に重視します。
1. 債務償還年数(Debt Coverage Ratio/Years)
意味: 現在の借入金を、企業の生み出すキャッシュフローで何年で返済できるかを示す指標です。
計算式: 債務償還年数 = {借入金 -( 売掛債権+棚卸資産 – 買掛債務)}÷{(経常利益+ 減価償却費 – 法人税等)}
目安: 10年以内が望ましいとされ、特に5年〜7年未満が適正とされます。年数が短いほど、返済能力が高いと見なされます。



数値が小さいほど健全(早く返済できる)です。 業種によって目安は異なりますが、一般的には10年以内が望ましいといわれております。なお、簡便的な算式として、「借入金÷キャッシュ」で計算することもあります。
2. インタレストカバレッジレシオ(Interest Coverage Ratio)
意味: 企業が利息を支払う能力(利息を賄う余裕)を示す指標です。
計算式: インタレストカバレッジレシオ= (営業利益 + 受取利息 + 受取配当金)÷ 支払利息
目安: 1.0を下回ると、利息支払い能力に問題があると見なされます。2~3が標準的です。
3. 償却前営業利益(EBITDA)
意味: 企業の本業から生み出す利益を示す指標で、キャッシュフローに近いとされます。
計算式: 償却前営業利益= 営業利益 + 減価償却費
ポイント: 減価償却費は過去の投資の費用処理であり、資金流出を伴わないため、キャッシュフローを見る上で重要です。
返済能力向上のための具体的な方法
利益を増やすことが最も基本的な方法です。また、借入金を減らすために繰り上げ返済をすることも、債務償還年数やインタレストカバレッジレシオに良い影響を与えます。ただし、無理な繰り上げ返済はキャッシュフローを悪化させる可能性があるため、注意が必要です。
3. 経営者自身の評価(熱意と危機管理能力)
融資審査は、数字だけでなく「人対人の付き合い」であり、経営者の人物像が非常に重要視されます。特に創業融資では、過去の実績が少ないため、経営者の信頼性や覚悟が最大の評価材料となります。
審査担当者は、創業計画書だけでは見えない、あなた自身の「中身」を面談で試します。
信頼を勝ち取るためには、準備と態度が重要となるのです。
A. 信頼性の証明:自己資金と信用情報
1. 自己資金の準備と「積立の経緯」
制度上、自己資金要件が撤廃されたとしても、実務上、自己資金は「本気度・計画性の証明」として極めて重要となります。必ず見られる項目でもありますので、コツコツと備えておきましょう。
目標目安
必要資金の1/3程度を自己資金として準備している方が通りやすい傾向があります。
重要なのは継続性
直前にまとまった金額を入金する「見せ金(ミセキン)」は、通帳を見られることによりすぐにバレるため、信頼性を疑われ審査がストップする原因となります。半年〜1年かけて毎月コツコツと積み立ててきた実績こそが、何よりの信頼材料となります。通帳のコピーを提出する際は、貯蓄経緯を説明できるように整理しておきましょう。
2. 個人の信用情報の管理
経営者個人の信用情報は、知らないうちに照会されています。
NG行為
クレジットカードの延滞、携帯料金の未払い、税金(住民税など)の滞納は、「この人にはお金を貸せない」と判断される決定的なマイナス要素です。
回避策
心当たりのある場合は、事前に「CIC」などで自身の信用情報を確認し、整理しておくことを強く推奨します。
B. 面談対策:熱意と危機管理能力のアピール
1. 計画への理解度と一貫性
審査官は必ず「この創業計画書、ご自身で書かれましたか?」と尋ねます。これは、事業の中身を自分で考え、理解しているかを確認する意図があります。税理士などの専門家 に相談するのは有効ですが、最終的には自分の言葉で、収支計画の数字の根拠や競合との差別化ポイントを明確に説明できることが最低条件です。書類の内容と面談での発言に矛盾がないよう、準備しておきましょう。
2. 熱意と継続できる姿勢
創業の動機(なぜその業種を選んだのか、なぜ今なのか)は、あなたの本気度と信頼性を伝える鍵です。アピール例としては、前職での経験や課題意識が、新しい事業とどう繋がっているのかを具体的に語ります。単なる「夢」ではなく、現在のスキルと事業との接点を明確にすることが大切です。
3. 危機管理能力の提示 リスク耐性と対応策の有無
危機管理能力の提示 リスク耐性と対応策の有無は、経営者として特に評価されます。 想定質問される質問としては、「売上が計画通りにいかなかった場合、どうしますか?」などがあります。模範回答としては、例えば、「赤字が○ヶ月続いた場合、役員報酬のカット、広告費の見直し、または赤字でも3ヶ月回せる運転資金を準備済みです」など、具体的な仮説と対策を用意しておきましょう。
4. 非言語コミュニケーションの重要性
見た目、態度、話し方といった非言語的な要素も、経営者としての信頼を測る上で重要です。例えば、服装はスーツが無難であり、清潔感のある格好を心がけるや、緊張していても、基本の挨拶や、聞かれたことに対して端的に答える力は、印象を大きく左右します。これも事前準備で大きく変わってきます。



銀行融資を成功させるための秘訣は、小手先のテクニックではなく、誠実な準備と伝える力に集約されます。
融資は、試験ではありません。信頼の構築プロセスです。
金融機関は、あなたが「この事業を成功に導く覚悟があるか」、「責任ある経営者として、いかなる危機にも対応できるか」を見ています。
今回解説した3大原則(資金使途、返済能力、経営者評価)に基づき、あなたの事業の可能性と、それを実現するための論理的な計画を、自信を持って伝えてください。そのための準備こそが、あなたの事業を成功に導く確実な一歩となるはずです。相談できる税理士がいない場合には、お気軽にこちらまでお問い合わせください。

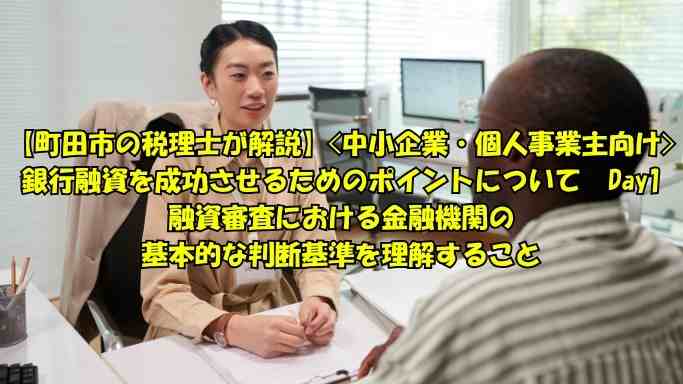








コメント