 ミミレイドン
ミミレイドンボス、おはようございます!
小規模企業共済って、この業界に入ってからよく聞きますが、名前が堅くて難しそうですよね。本当に節税になるのでしょうか?



確かに、名称だけ聞いたら難しそうですよね。でも、小規模企業共済については、余剰資金があれば、加入することをお勧めしています。
それでは、本日は小規模企業共済について、基礎からわかりやすく解説していきます。
今回の記事は次の人におすすめの記事となります。
• 毎年、税金の支払いが重荷だと感じている個人事業主や経営者の方
• 将来の退職金・老後資金に不安を感じている小規模企業の方
• 小規模企業共済に加入すべきか、迷っている初心者の方
今回の記事を読んで、無理のない範囲で加入をご検討ください。
1. 導入
事業が成長し、利益が伸びれば伸びるほど、ずっしりと重くのしかかるのが所得税と住民税です。特に、個人事業主や中小企業の経営者は、大企業の会社員が享受できるような充実した退職金制度を自分で整備することが難しいという課題があります。
こうした課題を一気に解決できる、まさに「一石二鳥」の公的制度が、小規模企業共済です。
この制度の最大の魅力は、「積み立てた掛金が全額所得控除になる」という、他にはない強力な節税メリットにあります。事実、この制度を活用している方の多くは、「退職金の準備」という建前よりも、「節税目的」で加入しています。
まずは、このお得な制度の全体像を把握しましょう。
2. 制度の概要:「経営者の退職金制度」の仕組み
運営元は国の中小機構で安心
本制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。国が運営している制度であるため、日本が崩壊でもしない限り、なくなることがなく、破綻するリスクはほとんど無いと言って良いでしょう。
2025年3月で約169万人の方が加入しており、資産運用残高は約11兆9,195億円にものぼります。



「国が運営しているから絶対に破綻しない」といった断定はできません。公的制度として法令に基づく安定運用が図られているとご理解ください。
掛金は柔軟に設定・変更が可能
掛金は月額1,000円から最大70,000円まで、500円単位で自由に設定できます。
- 増額・減額の自由度: 加入後も、経営状況に応じていつでも掛金を増額・減額できます。
- 納付方法: 毎月払い(月払い)のほか、年1回(年払い)や年2回(半年払い)でまとめて支払うことも選択可能です。
- 前納制度: 1年以内の前納分についても所得控除の対象となります。特に年末に駆け込みで節税したい場合に有効な手段です。
運用方法と予定利率
小規模企業共済は投資ではなく積み立てを前提とした制度であり、自分で運用する必要はありません。
積立金は、予定利率(2025年3月で年0.9%)をもとに運用されます。これはリスクを低く設定された商品と言えます。
共済金の種類
退職や廃業の理由によって、受け取れる共済金の種類が異なります。廃業や老齢による受取が、任意解約に比べて有利な税制優遇を受けることができます。
| 共済金の種類 | 請求事由(個人事業主の例) | 特徴 |
| 共済金A | 事業の廃業、死亡、親族への事業譲渡 | 最も優遇され、掛金元本に利率と運用益が加算されます。 |
| 共済金B | 65歳以上かつ15年以上掛金納付(老齢給付)、または疾病・負傷による退任/廃業 | 事業継続中でも受取可能です。 |
| 準共済金 | 法人成りなどで加入資格を喪失した場合 | 受取額は掛金とわずかな運用益のみで、一括受取のみです。 |
| 解約手当金 | 任意解約、または12か月以上の掛金滞納による機構解約 | 最も受取額が低く、元本割れのリスクがあります。 |



任意解約は制度趣旨(退職金準備)に反するため、設計上不利になってしまうということですね。短期での任意解約は原則として損失につながってしまうので、注意が必要ですね。
3. メリット
小規模企業共済に加入するメリットは多岐にわたります。
メリット1. 掛金が全額所得控除になり、節税効果が絶大
これが最大の魅力です。支払った掛金全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象となる所得から控除されます。例えば、年間最大額の84万円(月7万円)を積み立てた場合、その84万円に対して所得税と住民税が課税されなくなるため、その分の税負担が軽減されます。



この掛金は事業の経費にはできませんが、個人の所得控除として活用することで、所得税・住民税を節税できるのです。
メリット2. 共済金受け取り時の税制優遇
積み立てた共済金を受け取る際にも、税制上の大きな優遇措置が適用されます。
- 一括受け取りの場合: 「退職所得」として取り扱われ、「退職所得控除」1/2に軽減されるため、税負担が大幅に軽くなります。
- 分割受け取りの場合: 「公的年金等の雑所得」として扱われ、こちらも公的年金等控除(年金をもらっている人が税金を計算するときに、一定額を差し引いてくれる仕組み)の適用を受けられます。
現役時代に高い税率で控除を受け(節税)、退職時に低い税率で課税される(優遇)ため、トータルでの節税効果が大きくなります。
メリット3. 長期加入で元本以上に増える
小規模企業共済は、長期で掛金を納め続けることで、掛金総額以上の共済金を受け取れる設計です。特に、20年以上掛金を納め続ければ、解約手当金を含め、掛金総額に対して100%以上の解約手当金(または共済金A・B)を受け取ることが可能となります。掛金の合計が100万円だった場合、解約時に最大120%相当額(120万円)が戻ってくるという試算もあります。
メリット4. 低金利の貸付制度を利用できる
万が一、事業で急な資金が必要になった場合でも、加入者は納付した掛金の範囲内で、低金利の貸付制度を利用できます。
- 金利の低さ: 一般貸付けの年利は1.5%と低く設定されています。傷病・災害時や創業・転業時などの場合は年0.9%の特別金利が適用されるケースもあります。
- 審査の優位性: 担保や保証人が不要で、他社からの借入れがあっても本人確認のみで審査がないため、急な資金ニーズにも迅速に対応できる柔軟性に優れています。
メリット5. 差押えから保護される
共済金の受給権は、差押禁止債権として保護されます(国税等滞納の差押えなどの例外あり)。これにより、万が一事業が失敗した場合でも、老後資金のすべてを失うリスクを回避できます。
メリット6. 共同経営者や内縁関係者も対象に
個人事業主の共同経営者(1人の事業主につき最大2人まで、一定条件あり)も加入が可能です。また、通常の相続では難しい内縁関係者にも、遺書なしで財産(共済金)を遺すことができます。
4. 節税効果の目安
小規模企業共済の節税効果は、加入者本人の課税所得(所得から各種控除を引いた金額)と、設定した掛金によって大きく変わります。所得税は累進課税制度を採用しているため、所得が高い人ほど税率が高くなり、節税効果も大きくなります。
掛金の全額所得控除による節税額一覧表
| 課税される 所得金額 | 加入前の税金 | 加入後の節税額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 住民税 | 掛金 月額 1万円 | 掛金 月額 3万円 | 掛金 月額 5万円 | 掛金 月額 7万円 | |
| 200万円 | 104,600円 | 205,000円 | 20,700円 | 56,900円 | 93,200円 | 129,400円 |
| 400万円 | 380,300円 | 405,000円 | 36,500円 | 109,500円 | 182,500円 | 241,300円 |
| 600万円 | 788,700円 | 605,000円 | 36,500円 | 109,500円 | 182,500円 | 255,600円 |
| 800万円 | 1,229,200円 | 805,000円 | 40,100円 | 120,500円 | 200,900円 | 281,200円 |
| 1,000万円 | 1,801,000円 | 1,005,000円 | 52,400円 | 157,300円 | 262,200円 | 367,000円 |
- 「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
- 税額は令和6年10月現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割については、5,000円としています。
- 記載の内容は目安であり、将来の税額を保証するものではありません。



任意の金額で試算を希望される場合には、「共済金試算シミュレーション」をご活用ください。
5. 損をするケース:絶対に避けたい「元本割れ」のリスク
小規模企業共済は優良な制度ですが、「誰でも、どんな使い方をしてもお得」というわけではありません。特に以下のケースでは、思わぬ損失を被るリスクがあります。
ケース1. 20年未満での「任意解約」
最大のデメリットであり、絶対に避けたいのが元本割れのリスクです。
小規模企業共済は、掛金納付月数が240ヵ月(20年)未満で、自己都合による任意解約をした場合、払い込んだ掛金の総額よりも受け取る共済金が少なくなり、元本割れが発生します。



任意解約は、制度の本来の趣旨(退職金準備)に反するため、非常に厳しい設計になっています。12ヵ月未満の納付月数で任意解約した場合、解約手当金は受け取れず、掛け捨てになってしまいますので、ご注意ください。
ケース2. 所得が低い場合
所得が極端に低い場合、所得税率も低いため、掛金を積み立てた際の節税効果が限定的になります。課税所得が少ない場合、控除の恩恵を十分に享受できない可能性がありますので、ご自身の事業プランを基に慎重に検討しましょう。



積立時の節税メリットが小さいにもかかわらず、将来受け取り時に課税される税率が高いと、トータルで損をすることもあり得ますね。。。
ケース3. 法人経営者が役員報酬を増やした場合
法人経営者が節税目的で掛金を増やすために役員報酬を増額すると、社会保険料の負担が増加し、結果的に損をする可能性があります。具体的には、 社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)は、法人負担と個人負担を合わせると、報酬に対して約30%に達します。



増えた社会保険料の負担が、所得税・住民税の節税効果を上回ってしまうと、トータルコストが増加してしまうということですね。事前シミュレーションは必須ですね!
6. 注意点
損をせず、この制度を最大限に活かすために、以下の点に注意してください。
1. キャッシュフローに余裕を持つこと
長期的な加入が前提の制度であるため、事業の運転資金や生活費に影響を与えない範囲で掛金を設定することが重要です。
- もし資金繰りが厳しくなり、掛金を減額したり掛止めしたりすると、その減額・掛止めされた分はその後運用されず(金利がつかないまま放置)、将来受け取れる金額が少なくなってしまうためです。
- 一時的な資金不足には低金利の貸付制度(年1.5%など)を利用するなど、解約せずに継続する工夫が賢明です。
2. 受け取り時の課税時期を理解する
小規模企業共済は、「課税を先送りにできる制度」です。掛金支払時には税金がかかりませんが、受け取った共済金には必ず課税されます。



メリットの2でも記載しましたが、積み立てた資金を取り崩す際には、「退職所得控除」や「一時所得」として課税される仕組みが適用されます。税負担は大きく抑えられますが、受取時に税金はかかるということを認識しておきましょう!
3. iDeCoなど他の退職金制度との受取調整
iDeCo(個人型確定拠出年金)など、他の退職金制度を併用している場合、共済金の受け取りの順番やタイミングを間違えると、退職所得控除が減らされ、手残りの額が大きく変わってしまう可能性があります。
推奨される受取順序としては、iDeCoを先に受け取り、その後5年以上経過してから小規模企業共済を受け取るのがおすすめです。理由としては、iDeCoや一般の退職金の場合、前年以前19年以内に他の退職金を受け取っていると控除が調整されるルールがあるのに対し、小規模企業共済の調整期間は「前年以前4年」と短いためです。5年以上空けることで、控除が減らされずに済みます。
4. 法人役員は社会保険料の上限に注目
法人経営者で役員報酬を増やして加入する場合、社会保険料の負担増を避けるため、社会保険料の上限を超える役員報酬を設定しているタイミングで掛金を増やすのが、節税効果を最大化する戦略です。具体的には、健康保険料の上限(月額136万円以上)や厚生年金の上限(月額67万円以上)を超えた報酬部分に掛金を充当することで、社会保険料の負担増を抑えることができます。
7. 加入条件:加入資格と手続き
小規模企業共済は、その名の通り「小規模な事業者」を対象としています。
加入資格の主な要件
加入できるのは、以下の2つの条件を満たす、個人事業主、共同経営者、または会社役員です。
1. 事業規模(従業員数)が以下を満たしていること
- 20人以下:建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)など。
- 5人以下:商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)、弁護士法人・税理士法人などの士業法人。



補足となりますが、ここでいう「従業員」は、常時雇用の正社員を指し、役員や個人事業主本人、家族従業員、パート・アルバイトは含まれません。
2. その他の資格:
- 個人事業主:開業届を提出している方。
- 共同経営者:個人事業主1人につき最大2人まで加入可能(経営の意思決定や報酬を受けているなどの一定条件あり)。
- 会社等役員:株式会社や合同会社の役員などで、登記があること。
加入資格を失うケース(加入できないケース)
以下のような方は、原則として加入できません。
- 会社の実質的な経営者であっても、役員として登記されていない方。
- 生命保険の外交員や、配偶者・親族などの共同経営者の要件を満たさない専業従事者。
- 学業が本業の学生(全日制の高校生など)。
加入を検討するタイミング
小規模企業共済は、加入要件を満たしている時に一度加入しておけば、その後事業規模が大きくなり従業員数が増えても継続することが可能です。そのため、創業直後の規模が小さいうちに加入を検討し、手続きを済ませておくことを強くおすすめします。
加入手続き
手続きは非常に簡単で、主に以下の方法があります。
- オンラインで加入する: マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、窓口に出向くことなく自宅や職場から申込みが可能です。
- 窓口で加入する: 最寄りの金融機関(銀行、信用金庫、商工会、商工会議所など)の窓口で手続きが可能です。
主な必要書類
- 契約申込書、預金口座振替申出書(中小機構の様式)。
- 個人事業主の場合: 確定申告書の控え(事業開始直後の場合は開業届の控え)。
- 法人役員の場合: 役員登記が確認できる書類(登記簿謄本など)。
- 共同経営者の場合: 共同経営契約書の写し、報酬の支払い事実が確認できる書類など。
8. まとめ:将来を見据えた最適な資産防衛へ
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者にとって、これほどまでに節税効果と将来の安心を両立できる稀有な制度はありません。「退職金制度」として運営されているため、長期にわたり継続的に掛金を支出した場合には、「運用益+節税」の大きな恩恵を受けることができます。
成功の鍵は「長期継続」と「戦略」にあります。
- 最低20年間は解約しないことを前提に、無理のない掛金を設定しましょう。
- 特に高所得者の方は、節税効果が年間30万円以上に達する強力なツールです。
- iDeCoなどの他の制度との併用(特に受け取り順序)は、必ず事前に税理士などの専門家に相談し、最適な出口戦略を立ててください。
もし、現在の所得状況や、iDeCoとの併用など、具体的な計画に不安があれば、税理士に相談することで、節税効果を最大化し、安心して事業に集中できる環境を構築できます。



「節税になると聞いたからとりあえず入る」ではなく、元本割れとなるリスク(デメリット)をよく理解したうえで、加入をご検討ください。
また、加入する場合には、月額の掛け金をいきなりMAX(70,000円)とするのではなく、無理のない範囲内(1,000円からでも全然OK)で加入しましょう!相談できる税理士がいない場合には、お気軽にこちらまでお問い合わせください。

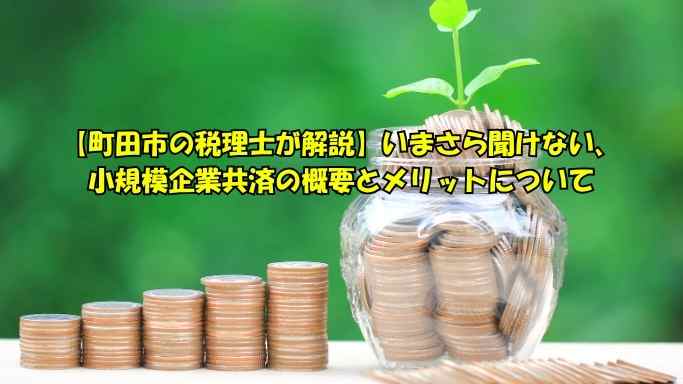








コメント